米金融政策の国際的衝撃
―― 量的緩和縮小と新興国経済
2014年8月号
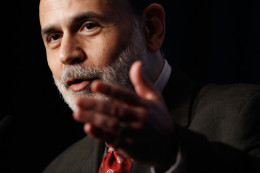
ユーロ圏以外の世界の貿易決済の大部分、そして外貨準備の60%には依然として米ドルが利用されており、当然、FRBの金融政策の変更は、グローバル市場に瞬時に大きな影響を与え、途上国へのキャピタルフローを極端に変化させ、途上国通貨の米ドルに対する価値は激しく変動する。この意味において、途上国の金融政策上の主権は事実上形骸化している。実際、連邦準備制度が資産の買い入れを縮小していくと示唆しただけで、投資家が資金を途上国から引き揚げて米国内の安全な投資先へと移動させたために、途上国の債券・通貨市場は大きな混乱に陥った。問題は、連邦準備制度が政策の判断にその国際的余波を考慮することは法的に想定されていないこと。そして、IMFを別にすれば、その余波を防ぐためのチェンマイ・イニシアティブやBRICS開発銀行構想が依然として実体を伴っていないことだ。・・・









