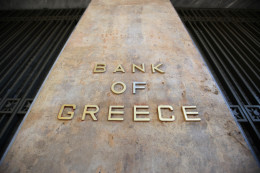そして今も同じ、政治風景
2012年6月号

紀元前64年にローマの執政官に出馬した実兄のマルクス・キケロのためにクィントゥス・キケロがまとめた選挙戦略メモ「選挙に関する小ハンドブック」の選挙指南は見事という他ない。この文章は、(君主論をまとめた)イタリアの作家で政治思想家のニッコロ・マキャヴェリがまとめた作品同様に、政治の過酷な現実を赤裸々に描いている。クィントゥスは、選挙に勝つために何が必要かについて、われわれキャンペーンアドバイザーが「信頼構築」と呼ぶやり方から始め、その後、候補者の支持基盤の本質と強さを分析し、特定グループをターゲットにする必要性を指南し、階級闘争とみられるのを避けるようにアドバイスしている。・・・