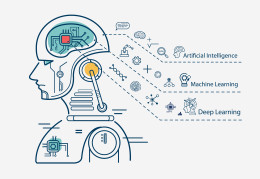威嚇、経済制裁、大言壮語で敵対勢力が譲歩するか、より優れた取引を手に入れられると期待するのがトランプの外交パターンだ。そうした戦術が何を引き起こすかを想定できず、逃げ場のない袋小路に自らを追い込むのもパターン化している。イランだけでなく、ベネズエラのケースでも「後退か軍事力行使」が残された選択肢となりつつあるし、中国と北朝鮮へのアプローチも同様に袋小路に追い込まれつつある。一方で、トランプが「戦争は望んでいない」とペンタゴンの高官に述べたとすれば、おそらく、彼はアメリカが不用意に紛争に巻き込まれていくリスクを予見し、それを回避したいと考えているのかもしれない。問題は、戦争を回避するのを助けてきた側近たちがもはやいないことだ。