文化遺産とナショナリズム
―― 文化遺産を人類が共有するには
2014年12月号
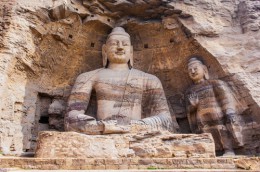
文化遺産の返還を求めることで、エジプトはファラオの時代と、イランは古代ペルシャ時代と、そしてイタリアはローマ帝国とつながっていることを示したいと考えている。しかし、これは文化保護主義につながる。狭義なアイデンティティーを強化するために文化遺産とその歴史を利用すべきではないだろう。文化遺産の返還を要求する流れは、文化財交流を否定するだけでなく、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ロンドンの大英博物館、パリのルーブル美術館などの世界的博物館の役割を否定することになる。博物館は、ある時期のある文化の美術品を、別の時期の異なる文化の作品と並べて展示することで、さまざまな世界と人々への関心と好奇心を刺激し、コスモポリタンな世界観を育む場所だ。文化財を、統治エリートの政治的アジェンダに左右される国家の遺産としてではなく、人類の遺産としてとらえる必要がある。









