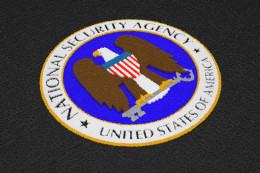LIBORスキャンダルの余波 ――LIBORは消失するのか
2014年1月号

LIBORとは、ロンドン銀行間市場において銀行が無担保資金を相互に提供する際に利用されるベンチマーク金利のことで、これまでは15の異なる満期と10の通貨で算出されてきた。世界の多くの銀行が、個人および法人向けのローン金利を設定する基本金利としてLIBORを利用してきたことからも明らかなように、短期金利のもっとも重要なグローバル・ベンチマークとみなされてきた。問題は、この金利が、トレーダーの利益、銀行の利益のために不正操作されていたことだ。すでに、バークレイズ、UBS、ラボバンク、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド(RBS)など複数の銀行が、自行の利益のために金利を操作する大規模な共同謀議を行っていたことが明らかになっている。当局によるペナルティだけでなく、顧客と投資家が金融機関を相手取って起こしている民事訴訟が現在争われており、今後、銀行側は膨大なコスト負担を強いられると考えられている。これによって銀行の体力が弱まるだけでなく、LIBORへの信頼そのものが失われつつある。アメリカではLIBORは廃止すべきだという考えが主流になっている。・・・・