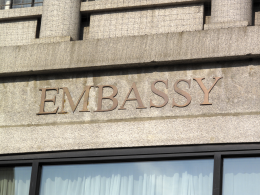サウジと米大統領選挙
―― クリントン、トランプ、リヤド
2016年5月号

「ジョージ・W・ブッシュ政権が残した(中東における)負の遺産を清算すること」を自らの中東における任務に掲げたオバマも、結局は負の遺産を次期米大統領に委ねることになりそうだ。シリア紛争への関与を躊躇い、イランとの核合意を模索したことで、サウジとアメリカの関係は極度に冷え込み、サウジでは、オバマは近年における「最悪の米大統領」と呼ばれることも多い。次期大統領候補たちはどうだろうか。サウジの主流派メディアは、イスラム教徒の(アメリカへの)移民を禁止することで「問題」を緩和できると発言したトランプのことを「米市民のごく一部が抱く懸念や不満を煽りたてる問題人物」と描写している。クリントンに期待するとしても、その理由は、彼女がトランプではないというだけのことだ。ますます多くのサウジ市民が、安全保障部門でのアメリカの依存を見直すべきだと考えるようになっている。・・・