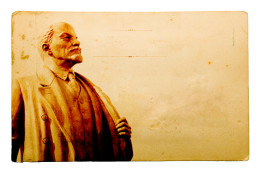プーチン主義というシステム
―― ロシア社会の変化にプーチンは適応できるか
2012年9月号

現在のロシア市民には一連の自由が与えられている。イケアで安い家具を買ったり、外国で休暇を過ごしたりと、いまやロシア市民はヨーロッパ中間層と生活の特質の多くを共有している。野心と才能のある者にとっては、モスクワはキャリアを築く大きな舞台だ。政治に関わらないかぎり、ありとあらゆる場所で選択肢が用意されている。この仕組みゆえに、プーチンのロシアには国を否定する者がいなかった。不満があるならいつでもロシアを離れることができた。プーチン主義は、ソビエト時代の硬直した管理システムよりもずっと狡猾で現代的なのだ。だがプーチン体制は共産主義とは違って、一貫した世界観を示しているわけではなく、安定と権力を維持するためにつくられている。逆に言えば、現状に不満を持つ新しい政治家や政治運動は、「根深いイデオロギーの壁を乗り越える」必要がない。これが、今後プーチン体制を脅かす最大の問題を作り出すことになるだろう。