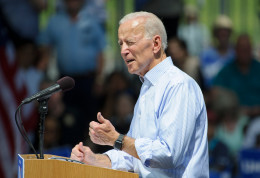石油をめぐるロシア対サウジの最終決戦
――エネルギー安保の分水嶺
2002年3月号

ロシアの石油企業によるロシア、中央アジア地域での開発が実現すれば、今後4年のうちに旧ソビエト諸国からの石油輸出の合計は、サウジアラビアの輸出にほぼ匹敵するものになる。九月十一日が、ロシア、アメリカ、石油輸出国機構(OPEC)にとって、全く新たな地政学状況を作りだしていることを、ロシアは、政治・経済的に立ち直る好機と捉えている。問題は、サウジアラビアが、ロシアの攻勢を阻止できるほどの、徹底した価格戦争を戦う余力があるかどうかだ。