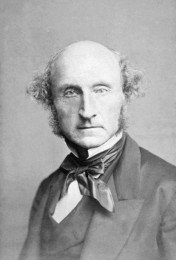高齢化社会という灰色の夜明け
1999年3月号

人口のほぼ一九%が高齢者で占められるフロリダ。これと同じ状況に先進諸国が直面するのは,そう遠い未来の話ではない。二〇〇三年にイタリア、二〇〇五年に日本、二〇〇六年にドイツがもう一つの「フロリダ」となる。イギリス、アメリカ、カナダもほどなくこれに続く。先進国社会の急速な高齢化がもたらす諸問題とコストは、投げだすのが合理的と判断しかねないほどにあらゆる意味で膨大である。各国の貯蓄は瞬く間に底をつき、財政が火の車になるだけではない。国内の政治力学、国際的資本の流れ、南北の力関係が逆転し、先進諸国から利他的な外交要素がなくなり、グローバルな安全保障が極度に不安定化する危険さえある。「自らの運命を管理し、より持続可能なコースへと道を変える時間的余裕があるうちに、現状を変革するしかない」。決断を下すべきは今で、「世界高齢化サミット」を開催し、この問題のための国際機関を設けることが急務だ。さもなくば、世界は「持続不可能な経済的負担と政治的・社会的苦難の後、悲痛な動乱の時代」へと突入することになりかねない。