イラクとアラブ世界の将来
2003年1月号
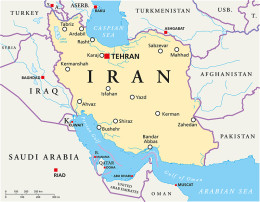
アラブの指導者たちは、心のなかでは「砂漠の嵐」を超える「完全な嵐」の到来を待ち望んでいる。短期間で決着がつき、サダム・フセイン追放の機会がつくり出されるような戦争を望んでいる。だが、これを「正義の戦争」と納得するアラブの民衆はほとんどいないだろうし、戦後には厄介な現実が待ち受けていることをアメリカは心しておくべきだ。
アラブ世界は、アメリカの罪をあげつらうことも、改革派を「外国勢力の手先」と切り捨てることもできる。それだけに、戦争をいかに戦うか、大いなる慎重さをもって臨まなければならない。









