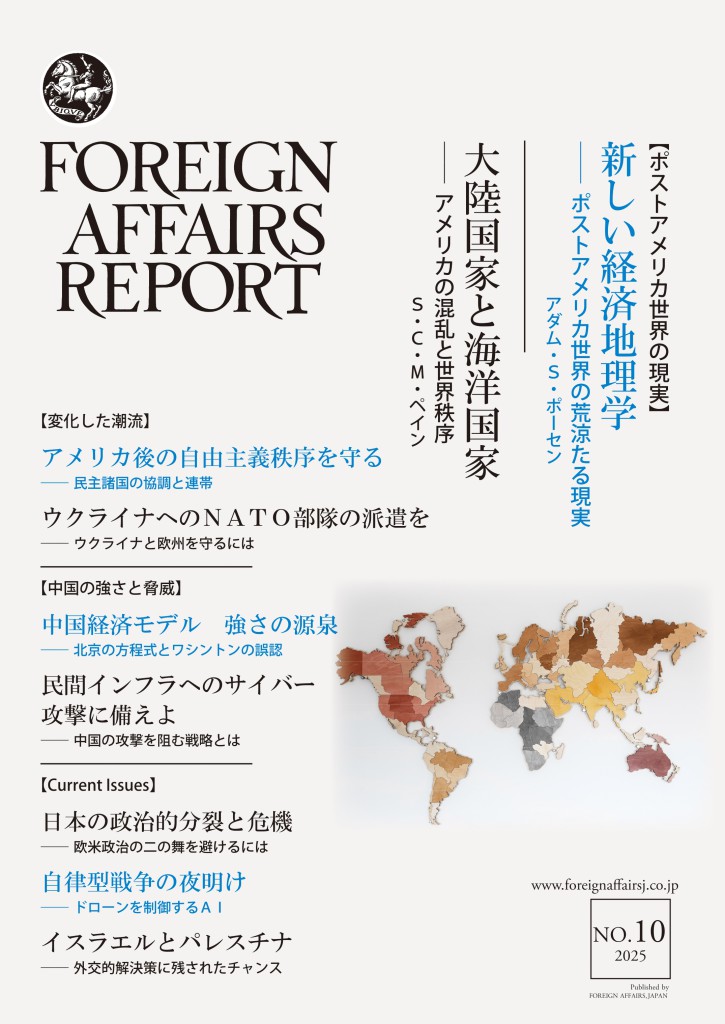
フォーリン・アフェアーズ・リポート2025年10月号 目次
ポストアメリカ世界の現実
-

新しい経済地理学
ポストアメリカ世界の荒涼たる現実雑誌掲載論文
トランプの新路線は、望ましい再編を促すと考える人もいる。だが、彼の政策を前に、各国の政府と企業が、最終的にニューノーマルを受け入れ、アメリカに利益がもたらされるという見方は、幻想にすぎない。それどころか、トランプの世界では、誰もが苦境に陥るし、アメリカも例外ではない。アメリカに最大の利益をもたらし、同盟国やパートナーに安心と繁栄をもたらしてきたシステムを彼は破壊してしまったからだ。特に、カナダ、日本、メキシコ、韓国、イギリスなど、米経済ともっとも密接に結びつき、これまでのゲームルールを忠実に守ってきた諸国の経済は大きなダメージを受けるだろう。トランプは楽園への道をつくり、カジノを建設した。だが、その駐車場はやがて空っぽになるはずだ。
-

大陸国家と海洋国家
アメリカの混乱と世界秩序雑誌掲載論文
中国やロシアのような大陸覇権国は、国際システムを巨大な勢力圏に分割すべきだと考える。一方、海洋で守られ、侵略される危険が小さい海洋国家は争うのではなく、富を蓄積することに専念する。領土ではなく富にパワーは根ざすとみているからだ。だが、現在のアメリカは、まるで大陸国家のように振る舞っている。あまりにも多くのアメリカ人が、海洋国家秩序の恩恵を当然視し、その欠点ばかりを指摘し、その過程で、地理的・歴史的な優位を無駄に浪費している。貿易障壁を築き、近隣諸国を脅し、国際機関を弱体化させるといった大陸国家のパラダイムに回帰すれば、アメリカは再起不能に陥るかもしれない。
-

新勢力圏の形成へ
大国間競争から大国間共謀へSubscribers Only 公開論文
中国やロシアと競争するのではなく、トランプ政権は中ロと協力することを望んでいる。トランプの世界観が大国間競争ではなく、「大国間共謀(great power collusion) 」、つまり、19世紀の「ヨーロッパ協調」に似ていることは、いまや明らかだろう。こうして、アメリカの外交路線は、ライバルとの競争から、温厚な同盟諸国をいたぶる路線へ変化した。他の大国から有利な譲歩を引き出すために、トランプがビスマルクのような外交の名手になる可能性もある。しかし、ナポレオン3世のように、よりしたたかなライバルに出し抜かれてしまうかもしれない。
-

支離滅裂な関税政策
壊滅的な間違いSubscribers Only 公開論文
関税で何でも解決できるとトランプは考えているようだ。しかし、関税が、彼が懸念する課題に対処するための最善の策であることはほとんどない。トランプ政権が指摘する米経済の問題の多くは、国内に病巣がある。貿易相手国を叩きのめしても、こうした根本的な問題の解決につながらないばかりか、米経済に害を及ぼすだけでなく、外国からの恨みや報復を助長し、被害を拡大させるだけだ。トランプ政権がその脅しを実行に移せば、その影響は、トランプが言う「小さな混乱」よりもはるかに破壊的なものになるだろう。
-

新しい世界の創造へ
もう過去には戻れないSubscribers Only 公開論文
トランプ政権の2期目が終わる頃には、古い秩序は修復不可能なまでに崩壊しているだろう。トランプ後を担う大統領は、多極化した、複雑な国際秩序を理解し、そこでアメリカがどのような役割を果たすかを決めなければならない。すべてを見直す必要がある。民主的価値へのコミットメントにはじまり、同盟関係、貿易、国防戦略までのすべてを再検証しなければならない。そうしない限り、ポスト・トランプの遺産という視点だけで米外交の将来を考え、これに過剰反応する危険がある。いまや、新しいテクノロジー、台頭する新興国が出現し、これに、長年の緊張が組み合わさることで、カオスが作り出されている。「ポスト・プライマシー」ビジョンの形成が急務だ。
変化した潮流
-

アメリカ後の自由主義秩序を守る
民主諸国の協調と連帯雑誌掲載論文
多くの国は、トランプ政権に媚びへつらい、米大統領を過度に称賛する努力を重ねてきたが、トランプを懐柔する戦略は失敗する可能性が高い。そうであれば、民主主義と旧来のルールに基づく秩序にいまもコミットする諸国は、国際関係を再構築し、アメリカの気まぐれから自らを隔離し、この極めて不安定な時代にあっても自分たちの自由を広く守る努力をするのが理にかなっている。実際、トランプの勢力圏構想が実現すれば、その国際環境で、アジア、ヨーロッパ、北米におけるワシントンの民主的同盟国がアメリカによって守られることはなくなるだろうし、民主諸国は世界の他の国々を合わせたよりもはるかに多くの核兵器を保有する米中ロという三つの大国と対峙することになる。
-

ウクライナへのNATO部隊の派遣を
ウクライナと欧州を守るには雑誌掲載論文
ヨーロッパのジレンマは、ウクライナを安心させるという決意を具体的な計画にどう結びつけていくかだ。アメリカの貢献が、よくても最小限のものに留まるとしても、ヨーロッパはウクライナの長期的な安全保障を確立するために、部隊を投入する必要がある。ウクライナへの侵略がNATO圏へ拡大してくるリスクを考慮し、ヨーロッパによるウクライナへの戦力展開はNATOの作戦、つまり、NATOによって計画・承認され、指揮される作戦として実施する必要がある。ヨーロッパの指導者が言うように、ウクライナの安全を守ることが、ヨーロッパの存亡を左右する。
-

もう誰も相手にしない
ポスト・アメリカ世界のアメリカSubscribers Only 公開論文
国際システムの他のアクターが(特定の言動に)どのように反応し、どのような流れを形作るかを予測することも外交手腕に含まれる。トランプ・チームには、そのような能力が欠落している。ワシントンのパートナーのなかには、友人であるアメリカが正気に戻ることを期待して、様子見をする国もあるかもしれない。しかし、もう元には戻れない。同盟国やパートナーの信頼と信用は修復不能なほどに損なわれている。いまや問うべきは、アメリカパワーの基盤だった米主導の協調的秩序から各国が手を引けばどうなるかにあるのかもしれない。
-

「アメリカの世紀」の終わり
ドナルド・トランプとアメリカパワーの終焉Subscribers Only 公開論文
この80年間にわたって、アメリカは、強制ではなく、他を魅了することでパワーを蓄積してきた。アメリカパワーを強化する相互依存パターンを破壊するのではなく、維持するのが賢明な政策だ。トランプが、米同盟諸国の信頼を低下させ、帝国的野望を主張し、米国際開発庁を破壊し、国内で法の支配に挑戦し、国連機関から脱退する一方で、それでも中国に対抗できると考えているのなら、彼は失意にまみれることになるだろう。アメリカをさらにパワフルにしようとする彼の不安定で見当違いの試みによって、アメリカの支配的優位の時代、かつてヘンリー・ルースが「アメリカの世紀」と命名した時代は無様に終わるのかもしれない。
-

同盟の流動化と核拡散潮流
次の核時代に備えよSubscribers Only 公開論文
最近の展開からも、ウクライナやその他の国々への防衛支援をめぐるアメリカのコミットメントが完全には信用できないことは明らかだろう。ワシントンが安全保障コミットメントを果たすとは信用しなかったフランスのドゴール大統領は正しかった。拡大抑止(核の傘)はまやかしであり、それを信じた人々はお人好しのカモだった。なぜフランスに倣って、核戦力を獲得して、国の安全を確保しないのかと多くの国がいまや考えているはずだ。このまま秩序が解体し続ければ、韓国は、おそらく、この拡散潮流に乗って最初に核を保有する国になるだろう。ソウルが核武装すれば、東京もそれに続き、最終的にはオーストラリアもこれに加わるかもしれない。ヨーロッパでも同じ流れが生じつつある。
-

同盟関係の崩壊と米国の孤立
同盟破壊という愚行Subscribers Only 公開論文
現在のアメリカは、イギリスが帝国の全盛期に経験した状況に直面している。世界最大の軍事大国であることは重い負担であり、それもあって、債務が驚くべき水準に膨らんでいる。中国をはじめとする野心的大国は、ますます高額化する軍備競争に資源を投入している。そして、歴史的に繰り返されてきた通り、他の諸国は古い大国を見捨てて、新興大国に乗り換え、その衰退を機に団結して対抗する誘惑に駆られている。トランプ政権が同盟国への敵対的な姿勢を継続し、長年のパートナーを侮辱し、経済的に損害を与えるような行動を続けるなら、アメリカの前にあるのは、ますます敵対的な世界になるはずだ。
-

ウクライナ支援を続けるべき理由
何が問われているのかSubscribers Only 公開論文
プーチンの攻撃を(われわれは)警告として受け止めなければならない。これは、暴君と悪漢が主導する世界、つまり、勢力圏に切り分けられた混沌とした暴力的な世界、いじめっ子が小さな隣人を踏みつける世界、そして侵略者が自由な人々に恐怖の生活を強いる世界の予告なのだ。つまり、私たちは歴史の分岐点にある。プーチンの侵略に今後も断固として立ち向かうのか、それともプーチンの思いのままにさせ、私たちの子や孫たちに、はるかに血なまぐさい危険な世界を生きることを宣告するのか。ウクライナが踏みにじられれば、ヨーロッパ全土がプーチンの影に脅かされることになる。
※このテキストは、キーウのウクライナ外交アカデミーで行われたスピーチからの抜粋。邦訳分はFAJによる翻訳・要約で、米政府の公式テキストではない。 -

いかに戦争を終わらせるか
ウクライナのNATO加盟を認めよSubscribers Only 公開論文
戦争を終わらせるには、ロシアにウクライナの一部領土を与えるのと引き換えに、北大西洋条約機構(NATO)へのウクライナ加盟を実現させる洗練された計画が必要になる。恒久的な平和を生み出すには、このような妥協をするしかない。「勝利しつつある」と考えているプーチンに和平交渉に入るように説得できても、トランプはゼレンスキーも説得しなければならない。これは大きなチャレンジになる。領土奪還を諦めるならば、これらの土地に住む市民も見捨てるのか、それともウクライナ西部への移住を保証するのか、ゼレンスキーは決断しなければならない。そして、トランプ自身、和平交渉を実現するために、ウクライナ支援を維持(さらには拡大)する必要がある。
中国の強さと脅威
-

中国経済モデル 強さの源泉
北京の方程式とワシントンの誤認雑誌掲載論文
北京は今後を左右する経済戦略部門を選び、そこに補助金を注ぎ込んだ。しかし、これだけでは北京の産業政策は説明できない。レジリエントな技術大国となるために必要な奥深いインフラを整備したからこそ、中国は成功した。パワフルな電力網とデジタルネットワークを中核とするイノベーション・エコシステムを形作り、高度な製造知識をもつ大規模な労働力も育んだ。これが大きな力となっている。関税や規制でワシントンが中国の成長のタイミングを遅らせようとしても効果はない。ライバルを弱体化させる方法を考える時間を減らし、ワシントンは、自国をもっとも活力ある姿にする方法を考えるべきだろう。
-

民間インフラへのサイバー攻撃に備えよ
中国の攻撃を阻む戦略とは雑誌掲載論文
中国のサイバー支配は、テレコミュニケーション部門の諜報活動にとどまらない。アメリカのエネルギー、水道、パイプライン、交通システムから中国のマルウェアが発見されている。目的は、米市民の日常生活や米軍の作戦行動を妨害するための破壊工作にあるようだ。動員を遅らせたり、航空管制システムを妨害したりすることができる。実際、台湾危機のタイミングで、中国が、アメリカの鉄道網を寸断したり、東海岸全域で停電を引き起こしたりすれば、どうなるだろうか。中国が優位にあるサイバー空間で、防衛を強化していくカギは、現実世界をサイバー空間に忠実に再現できるデジタルツインを応用することかもしれない。
-
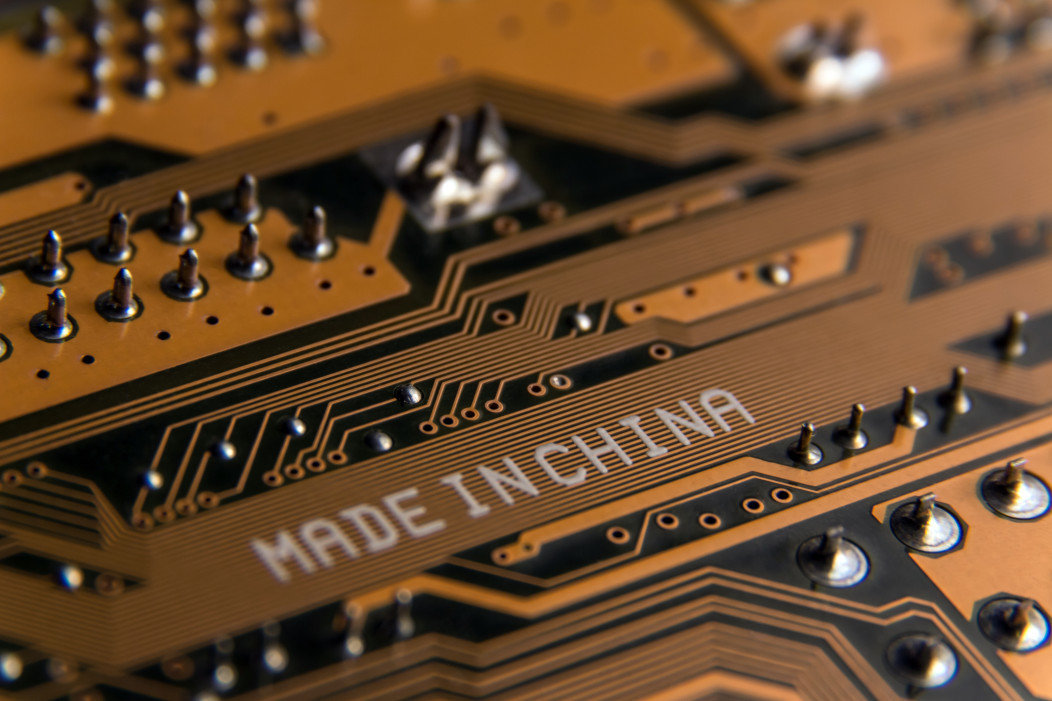
中国技術革命の本質
大量生産と「プロセス知識」Subscribers Only 公開論文
最先端の技術を持ちながら、なぜアメリカは中国に世界のソーラー産業覇者の座を奪われてしまったのか。理由は、研究開発やイノベーション、そして製品ブランディングなどの付加価値の大きい部門を重視する一方で、生産プロセスをアウトソースして軽視してきたからだ。一方、中国は、限界まで生産能力を高めることで、大量生産そのものがもたらす学習プロセスを技術イノベーションに組み込んで進化させた。このような「プロセス知識」と呼ばれるスキルが、中国を技術イノベーションの中枢へ押し上げた。先鋭的な科学技術だけでなく、中国のように労働力を活用し、製品をより良く、効率的に製造することをアメリカは学ぶべきだ。製造プロセスは、発明や研究開発というスリリングな領域のサイドショーではない。それは、技術進化に不可欠の要素なのだ。
-

イノベーション戦争
衰退するアメリカの技術的優位Subscribers Only 公開論文
北京は「戦争という最終手段をとらずに目標を達成するツールとしてテクノロジーのイノベーションに挑んでいる」。5Gの無線インフラを世界各地で販売し、合成生物学に取り組み、小型で高速なマイクロチップの開発を急いでいる。これらはすべて中国のパワーを強化するための試みだ。当然、ワシントンは視野を広げ、超音速飛行、量子コンピューティング、人工知能などの明らかな軍事用途をもつテクノロジーだけでなく、マイクロエレクトロニクスやバイオテクノロジーなど、これまでは本質的に民生用とみなされてきたテクノロジーも支援し、民間部門が投資しない分野に資金を提供する必要もある。
-

中国モデルとは何か
権威主義による繁栄という幻想Subscribers Only 公開論文
途上国は「リベラルな民主主義」よりも「中国モデル」に魅力を感じ始め、習近平自ら、「他の諸国は人類が直面する問題への対策として、中国のやり方に学ぶべきだろう」と発言している。当然、中国モデルが注目を集めているが、それがどのようなものかという質問への答は出ていない。その経済的成功が何によって実現したかも定かではない。現実には、鄧小平期の北京が、官僚制度の改革を通じて、地方の下級官僚たちが、現地の資源を用いて経済開発を急速に進めるのに適した環境を提供したことが、中国モデルの基盤を提供している。だが、こうした特質は民主国家にとっては、おなじみのものだ。懸念すべきは、中国モデルが欧米や途上世界で広く誤解されていること、そして中国のエリートたちでさえ、中国モデルを誤解していることだろう。
-

中国のエネルギー地政学
クリーンエネルギーへの戦略的投資Subscribers Only 公開論文
トランプ政権が石油・天然ガスを重視し、パリ協定に背を向けるなか、すでに中国は戦略的にクリーンエネルギー大国の道を歩みつつある。新エネルギー戦略が成功すれば、世界の気候変動との闘い、さらには地域的同盟関係や貿易関係の双方において、中国はアメリカに代わる最重要国に浮上する。クリーンエネルギーテクノロジーの輸出国として中国は、各国に石油・天然ガスの輸入量さらには二酸化炭素排出量を減らす機会を提供できるし、相手国政府との関係も強化できる。冷戦期のアメリカが、ソビエトとの宇宙開発競争に敗れた場合の経済的・軍事的余波を認識して、対抗策をとったように、ワシントンは中国の再生可能エネルギーへの移行にも、同様の対策をとるべきだろう。アメリカは、世界のエネルギー市場における優位を手放すリスクを冒している。
-

次なるサイバー超大国 中国
主導権はアメリカから中国へSubscribers Only 公開論文
いずれ中国はサイバースペースを思いどおりに作り直し、インターネットの大部分は、中国製ハードウエアを利用して中国製アプリで動くようになるかもしれない。「難攻不落のサイバー防衛システム」を構築し、インターネット統治についての中国モデルの影響力を強化するだけでなく、人工知能(AI)や量子コンピュータ部門でも世界のリーダーになることを目指し、大がかりな投資をしている。途上国では、中国の「サイバー主権」統治モデルが大きな支持を集めているし、中国は、第5世代モバイル通信システム(5G)の技術標準を確立したいと考えている。もはやワシントンがいかに手を尽くそうと、今後、サイバースペースの主導権がアメリカから中国へシフトしていくのは避けられない。
Current Issues
-

日本の政治的分裂と危機
欧米政治の二の舞を避けるには雑誌掲載論文
トランプが世界の貿易システムを覆し、同盟国にもっと国防を強化するよう促し、アジアにおける米軍のプレゼンスを見直すことを検討するなか、日本はアメリカとの関係を再定義していく必要がある。問題は、日本の政治的中枢が弱体化していることだ。自民党は内部分裂し、連立相手の支持基盤も揺らぎ、野党にもまとまりがない。一方で、ポピュリストの右派政党が台頭している。日本の統治にとって最大の問題は、権力が分散化し、それによって手詰まり状況が生じていることだ。こうした環境における政治的リーダーシップの欠落が、日本が地政学的な地殻変動に対応するのを難しくしている。
-

自律型戦争の夜明け
ドローンを制御するAI雑誌掲載論文
ロシアもウクライナも、ハードウエアやソフトウエアそして戦術をよどみなく改良し続けているために、この戦争は息を呑むようなスピードで進化している。膨大な数の監視用ドローンを飛ばすことで、ほぼすべての部隊の動きが可視化され、前線付近で動くものは、それがなんであれ、数分以内に攻撃される。ドローンが敵のドローンと戦うケースも増えている。自律型ドローンスウォーム(大編隊)の攻撃を調整できるAIの開発がいまや焦点とされている。戦争の第1段階はハードウエアの有無が戦況を左右し、双方が新しいタイプのドローン、ペイロード、弾薬に投資したが、次の段階はソフトウエアが焦点になるだろう。
-

イスラエルとパレスチナ
外交的解決策に残されたチャンス雑誌掲載論文
イスラエルは厳しい選択を迫られている。パレスチナとの妥協と平和的共存を誠実に模索するか、長期的な繁栄に必要な国際的支持を失うリスクを冒すかのいずれかだ。多くのイスラエル人は、武装勢力がパレスチナを活動拠点にすることを恐れ、パレスチナ国家の樹立には強く反対しているが、無期限の占領という現状は、イスラエルを国際的に孤立させ、失うものがないと感じる人々によるテロに永遠に直面することになる。ガザや西岸からパレスチナ人を強制移住させることもヨルダンや他の近隣諸国の不安定化を招きかねないし、アラブ諸国との関係も悪化する、国をもつことがパレスチナにとって有益であることは言うまでもないが、イスラエルにとっても有益であることを認識する必要がある。
-

日はまた昇る
日本のパワーは過小評価されているSubscribers Only 公開論文
「日本は、経済的繁栄を中国に、安全保障をアメリカに依存しすぎている」と悲観する見方が市民の間で大きくなっている。さらに、2020年9月の安倍首相の突然の辞任によって、国内の安定した指導体制や先を見据えた外交の時代が終わるかもしれないという懸念も浮上しつつある。地政学的ライバルが大きな流れを、そしてパンデミックが混乱を作り出すなか、ワシントンは、再び、日本のポテンシャルをまともに捉えず(この国を無視する)誘惑に駆られるかもしれない。しかし、日本の戦略的選択は、日本の将来だけでなく、米中間の激しい大国間競争の行方にも影響を与える。日本の時代は終わったとみなすこれまでの見方が、時期尚早だったことはすでに明らかだ。
-

驚異的なドローン革命
ウクライナからいかに学ぶかSubscribers Only 公開論文
ウクライナ軍の前線部隊は、ドローンの戦場におけるパフォーマンスを軍需企業に伝え、企業側はこれを基にシステムを常に改善し続けている。アメリカを含む世界のほとんどの国々は、兵器のフィードバックと改善という領域でウクライナに大きな後れをとっている。すでにウクライナとロシアは、ドローンなどの防衛技術にAIを徐々に組み込むことで、イノベーションをさらに進化させている。もしアメリカがウクライナ支援から手を引けば、実績のある防衛技術や戦場における知見、ロシアの軍事パフォーマンスに関するデータへのアクセスを失う危険がある。
-

中東での壮大なパワーゲーム
核合意とイスラエル覇権の間Subscribers Only 公開論文
イスラエルの軍事的成功、イラン系「抵抗の枢軸」の衰退とシリアにおけるアサド体制の崩壊が中東秩序を大きく揺るがした。ガザの占領拡大に加え、イスラエルはレバノン南部に自らの意思を押し付け、シリアの多くの地域に軍事侵攻した。そしていまや、イランを軍事攻撃することで、レバントでの勝利を湾岸にまで拡大したいと考えている。イスラエルが地域覇権を確立しつつあるかにみえたために、イスラエルとイラン間の新しいバランスを形作ろうと、湾岸諸国は、トランプが求める新たなイラン核合意を推進する主要なプレーヤーになった。そこでは、壮大な駆け引きが展開されていた。トランプは湾岸諸国の立場を優先し、イスラエルの意向を無視した。
-

ユダヤ人国家と民主国家を両立させるには
二極化するイスラエルの政治Subscribers Only 公開論文
いまや国家アイデンティティーや価値、ユダヤ主義、民主主義をめぐってイスラエルは二分され、ネタニヤフ政権はそのギャップを大きくする行動をとっている。実際、イスラエルの最終目的が「大イスラエル」なら、パレスチナ側にパートナーを見いだす必要はない。・・・一方、私たち(野党)にとって重要なのは、「ユダヤ人の民主国家」を維持することだ。そのためには、古代イスラエルの土地を二つの国に分けるしかない。イスラエルが(パレスチナの)領土を併合したら、民主国家としてのイスラエルと、ユダヤ人国家としてのイスラエルが衝突する。・・・「ユダヤ人的で民主主義のイスラエル」の実現が目的なら、(「大イスラエル」主義者が唱える)土地すべてを領土にすることはできない。二国家共存のなかでのイスラエルが必要だ。・・・二国家解決策が私たちの目標だと公言して、国際社会とパレスチナの信頼を勝ち取らなければならない。(聞き手はジョナサン・テッパーマン、フォーリン・アフェアーズ誌副編集長)。







