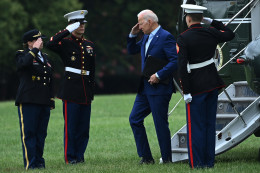ロシアの衰退という虚構
―― そのパワーは衰えていない
2022年1月号

人口減少や資源依存型経済など、ロシア衰退の証拠として指摘される要因の多くは、ワシントンの専門家が考えるほどモスクワにとって重要ではない。プーチン大統領が退任すれば、ロシアが自動的に対米対立路線を放棄すると考えるべきではない。プーチンの外交政策は、ロシアの支配層に広く支持されており、クリミア編入をはじめとする未解決の紛争も彼の遺産とみなされている。アメリカとの対立は今後も続くだろう。つまり、ワシントンには中国に焦点を合わせ、ロシアの衰退を待つという選択肢はない。アメリカのリーダーは、ロシアを衰退途上にある国とみなすのではなく、永続的なパワーをもつ大国とみなし、ロシアの本当の能力と脆弱性を過不足なく捉えて議論しなければならない。