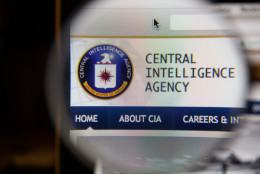リー・ファミリー後のシンガポール
―― リー・クアンユーのレガシーと都市国家の未来
2017年9月号掲載予定

1965年の独立以降、リー・クアンユーが中心となって組織した人民行動党政権は中央集権的な国家運営を行ってきた。その権力に対する監視体制も厳格ではなく、野党、市民社会、メディアは概しておとなしい。実際、この中央集権体制が効率的な統治を実現していると考える者は多く、シンガポール市民の大半は、「経済成長と引き換えに市民的・政治的自由が制限される」という暗黙の社会契約を長く受け入れてきた。だが、それも変化しつつある。すでに、シンガポールのさらなる発展にはさまざまな制約を緩和する必要があると考える改革派の要求とこれまでの中央集権型の枠組みを両立させるのは難しくなっている。近代国家シンガポールの原点を象徴するリー・クアンユーのオクスリー・ロードにある家の扱いをめぐるお家騒動は、まさに、この国の未来に関する二つのコースを描き出している。