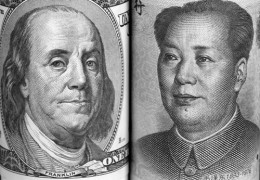信仰の時代における外交
――宗教的自由と国家安全保障
2008年5月号

宗教が世界的規模で台頭し影響力を強めつつある。だが、宗教とは本来、感情的かつ不合理なものであり、近代性とは相反するという根強い思い込みが、宗教と民主主義との関係についての明瞭な思考を妨げている。その結果、宗教的迫害に反対し、宗教を理由に拘束されている人物を解放することばかりにとらわれて、宗教的自由を促進するという目的が完全に忘れられてしまっている。
政策決定者は、宗教に対して経済や政治問題同様のアプローチをとる必要がある。つまり、宗教のことを、人間や政府の行動を駆り立てる重要なインセンティブとして認識しなければならない。政治的、経済的動機のように、宗教的動機も、破壊的、または建設的構造双方を増幅させる力を持ち、より劇的な結果を招き入れることが多いことを理解し、外交に宗教ファクター、つまり、宗教的自由の促進という要素を統合していく必要がある。