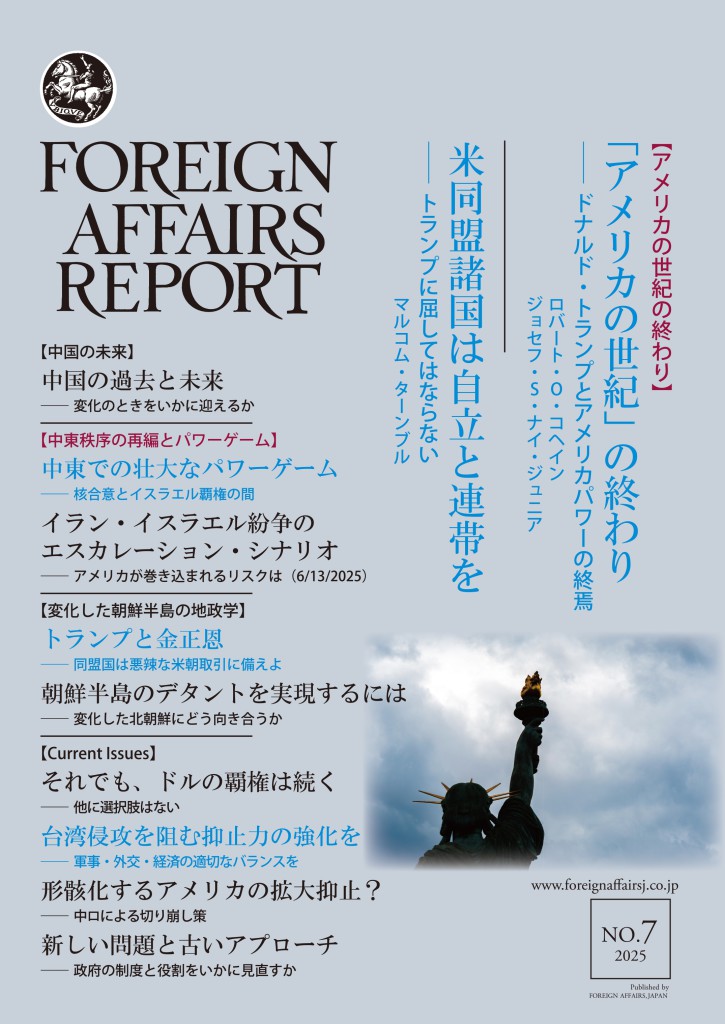
フォーリン・アフェアーズ・リポート2025年7月号 目次
アメリカの世紀の終わり
-

「アメリカの世紀」の終わり
ドナルド・トランプとアメリカパワーの終焉雑誌掲載論文
この80年間にわたって、アメリカは、強制ではなく、他を魅了することでパワーを蓄積してきた。アメリカパワーを強化する相互依存パターンを破壊するのではなく、維持するのが賢明な政策だ。トランプが、米同盟諸国の信頼を低下させ、帝国的野望を主張し、米国際開発庁を破壊し、国内で法の支配に挑戦し、国連機関から脱退する一方で、それでも中国に対抗できると考えているのなら、彼は失意にまみれることになるだろう。アメリカをさらにパワフルにしようとする彼の不安定で見当違いの試みによって、アメリカの支配的優位の時代、かつてヘンリー・ルースが「アメリカの世紀」と命名した時代は無様に終わるのかもしれない。
-

米同盟諸国は自立と連帯を
トランプに屈してはならない雑誌掲載論文
「原則を重視する寛大なアメリカ」を今も信じている人々にとって、いまは認知的不協和を引き起こすトラウマ的な状況にある。トランプ政権が作り出す現実は、はっきりしている。内外で法を顧みない行動をとり、各国へのいじめを繰り返し、協定や条約を破棄し、同盟国を威嚇し、独裁者に寄り添っている。米有権者は、この行動を最終的に(選挙で)判断することになる。だが、アメリカの同盟国はすでに心を決めているはずだ。トランプの威圧に屈する必要はない。同盟国が協力すれば、大きな影響力を行使できるし、ワシントンが作り出す大混乱に対抗できる。エマニュエル・マクロンが言うように、米同盟諸国は「いじめられない国」の連合を構築すべきだろう。
-

アメリカなき世界システム
新しい国際統治の形Subscribers Only 公開論文
トランプ政権は、アメリカがその形成に深く関わってきた条約や国際機関、経済システムに背を向けつつある。この状況がカオスや紛争につながっていくかは、これまで秩序を支えてきた、欧州や日本を含む、多くの国の行動次第だろう。世界が米主導の制度、条約、同盟から離れて他国が主導するシステムへ移行していく道筋はいくつか存在する。世界銀行などの既存の国際機関でアメリカの役割を代替することもできる。既存の国際機関と同じ機能の一部を果たせる代替システムをみつけることも、協力関係を維持してG9やG12のようなものを形作ることもできる。だが、何もしなければ、これまで以上に危険に満ちた世界で、手段も影響力もなく、狭義の短期的な利益を守るために奔走することになる。
-

さようなら、国際主義のアメリカ
トランプ時代の歴史的ルーツSubscribers Only 公開論文
トランプの「アメリカ第1主義」は、外交の初心者が犯した間違いではなく、アメリカのリーダーたちが戦後外交の主流概念から距離を置きつつあるという重要な潮流の変化を映し出している。先の大戦期及びその直後に成人した世代は、アメリカが世界をリードしなければ、いかに忌まわしい世界が出現するかを本能的に理解していた。これは、戦争で苦しんだ末に得た教訓だった。しかし、この世代の多くが亡くなり、具体的に秩序を形作った子どもの世代も少なくなってきている。これが、今後の米外交政策にもっとも重要な帰結を与えることは間違いない。トランプが大統領の座を退いても、「アメリカのリーダーシップなき世界」がどのような末路を辿るかを知る人々が支えたかつてのコンセンサスへアメリカが回帰していくことはない。残念ながら、不幸な結果を記憶している人々はもうすぐいなくなる。
-

トランプと競争的権威主義の台頭
米民主主義は崩壊するのかSubscribers Only 公開論文
アメリカの司法省、連邦捜査局、内国歳入庁(IRS)などの主要政府機関や規制当局をトランプの忠誠派が率いるようになれば、政府はこれらの政府組織を政治的な兵器として利用できるようになる。ライバルを捜査と起訴の対象にし、市民社会を取り込み、同盟勢力を訴追から守れるからだ。こうして競争的権威主義が台頭する。政党は選挙で競い合うが、政府の権力乱用によって野党に不利なシステムが形作られていく。政治家、ビジネス、メディア、大学、市民団体も権威主義政権の大きな権限と圧力を恐れて、立場を見直して声を潜める。競争的権威主義の台頭は、アメリカだけでなく、世界の民主主義にとって重大で永続的な帰結をもたらすことになるだろう。
-

ドナルド・トランプと権力政治の時代
同盟諸国はどう動くべきかSubscribers Only 公開論文
トランプは19世紀のパワーポリティックが規定する国際関係への回帰を明らかに思い描いている。同盟関係のことを、アメリカから雇用を奪う国々を保護するコストをアメリカに負わせる悪い投資だと考えている。関税引き上げなどの、経済的威嚇をパワーツールとして利用する彼のやり方は、強圧的秩序の幕開けを意味する。アメリカに譲歩しても、トランプがそれを評価することはない。アメリカの同盟国は強さを示さなければならない。トランプが理解するのは力であり、米同盟諸国が協力すれば、十分な力で立ち向かい、トランプ外交の最悪の衝動をけん制できるかもしれない。
-

ならず者の超大国
非自由主義的アメリカの世紀?Subscribers Only 公開論文
戦後秩序のなかで、ワシントンは多くの国に軍事的保護、安全なシーレーン、米ドルと米市場へのアクセスを提供し、引き換えに、これらの同盟諸国はアメリカへの忠誠を尽くし、自国の経済や政治の自由化に応じてきた。だが、アメリカ外交の底流をなしているのは、リベラリズムよりも、アメリカファーストの思想だ。(他の先進諸国の)急速な人口高齢化そしてオートメーション化の台頭によって、アメリカのリードはさらに堅固になり、パートナーへの依存レベルが低下すれば、アメリカは国際協調よりも「外交への取引的アプローチ」を重視する「ならず者の超大国」になるかもしれない。これまでの「アメリカ世紀」が、世界におけるアメリカの役割についてのリベラルなビジョンを基盤に構築されてきたのに対し、私たちの目の前にあるのは、「非自由主義的なアメリカの世紀の夜明け」なのかもしれない。
中国の未来
-

中国の未来を考える
「権威主義的繁栄」の影響力雑誌掲載論文
習近平体制は、欧米と対立する一方で、ロシアを助け、国内では監視体制を強化し、少数民族を抑圧してきた。だが、現状から直線的にとらえて中国の将来を考えるのは、今も昔も間違っている。20年後に中国を担うのは、今よりも開放的な時代を青春期に経験している、現在40代の若いエリートたちだ。民主的でも、リベラルでもないかもしれないが、未来の中国はそれでも世界に「権威主義的繁栄」という政治・経済モデルを提供できる国に進化しているかもしれない。地政学的・経済的大国を目指し、その過程で、「中国の本質」を見失わないという、清朝期の二つの願いを実現することに北京は成功するのかもしれない。もちろん、それには条件がある。
-
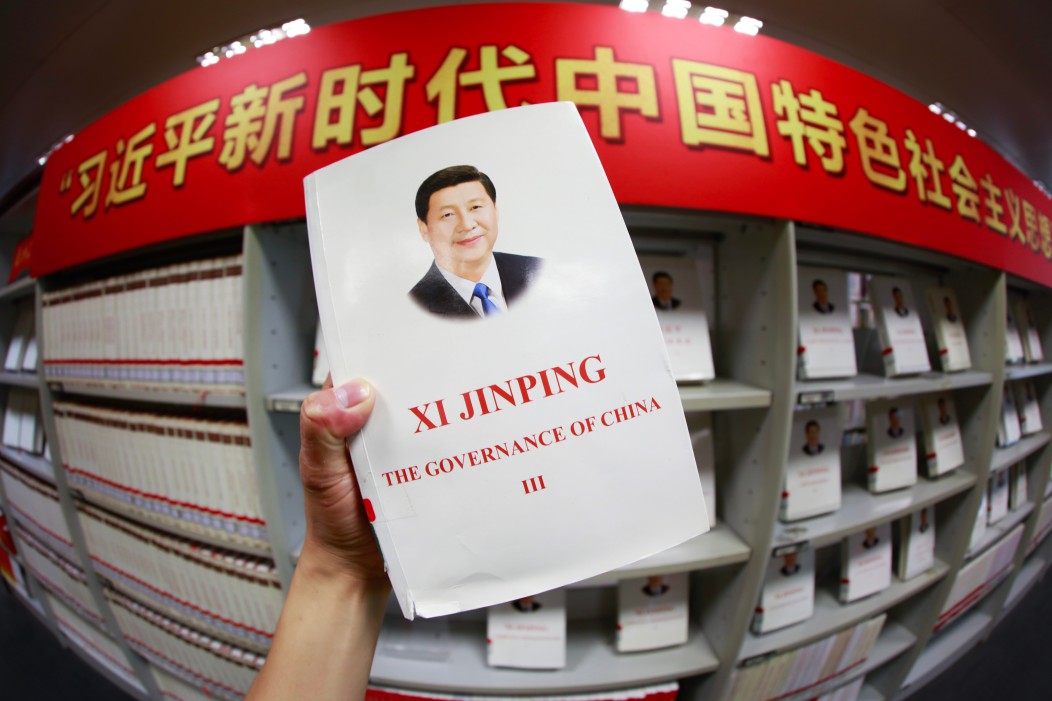
習近平思想と中国社会
マルクス主義と儒教の出会いSubscribers Only 公開論文
過去1世紀における中国の政治思想家たちは、未来の繁栄のためには、過去と完全に決別する必要があると考えがちだった。初期におけるマルクス主義の思想家たちは、「序列や儀礼、理想化された過去への回帰を重視する儒教思想」を激しく批判した。だが、中国の思想家や市民は、中国の伝統に即したやり方で政治環境の変化に対応することが重要だと、一貫して考えてきたようだ。実際、習近平思想のカギは、マルクス主義と儒教を結びつけていることだ。現代中国はマルクス主義を「魂」とし、素晴らしい中国の伝統文化を「ルーツ」と考えるべきだと習は語っている。中国社会が経済的停滞と没価値状況に苦しんでいるだけに、この、イデオロギーと国家アイデンティティーの再定義は、大きな意味合いをもつことになるかもしれない。
-

習近平の本質
奢りとパラノイアの政治Subscribers Only 公開論文
習近平は中国の政治派閥のすべてから反発を買っている。彼が伝統的な権力分配構造を破壊したことに憤慨し、その「無謀な政策が党の将来を危うくしている」と考えているエリートは少なくない。民間企業を締め上げ、政策の細部にまで介入して民衆を苦しめる統治スタイルへの社会の反発も大きい。いまや、天安門事件以降初めて、中国の最高指導者は政府内部の反対意見だけでなく、激しい民衆の反発と社会騒乱の現実的リスクに直面している。今後、統治スタイルがさらに極端になれば、彼がすでに引き起こしている内紛は激化し、反発は大きくなる。習近平が脅威を感じ、大胆な行動に出れば、ますます反発が大きくなるという悪循環が生じるかもしれない。・・・
-

The Clash of Ideas
アジアのナショナリズムと革命思想(1950年)Subscribers Only 公開論文
1930年代初頭、毛が引き継いだ共産党は衰退途上にあった。事実、1937年に日本が中国を侵略するまで、共産党は中国政治ではまったく目立たない存在だった。しかしその後共産党は、中国北方における愛国主義運動の指導的役割を担うようになった。外国の専門家が彼らを愛国主義者と呼んだのは間違いではなかった。外国の侵略者が家屋に火を放ち、虐殺行為を行っているさなかに、農民を組織するのは簡単ではなかったが、日本軍の行動が、結果的には中国北部の農民を中国共産党の懐へと送り込んだ。共産党側は準備万端調えて、農民が自分たちのところへ転がり込んでくるのを待っていればよかった。重要なポイントは、あえて地主階級への反対を前面に出すより、むしろ抗日戦への愛国主義を訴えるほうが、国内の青年知識層が呼びかけに応じる可能性が高いことを共産主義勢力が理解していたことだ。
-

アジア主義からナショナリズムへ
アジアにおける革命運動の変遷Subscribers Only 公開論文
第一次世界大戦期、アジアでは別の戦争が起きていた。ジャワ島では、中心部でもプランテーションでも労働者のストライキが起き、マレー半島のクランタン州では新税に対する反乱が発生した。サイゴンからスマトラ、シンガポールからラホールまで、抵抗思想が野火のような広がりをみせていた。反乱にはそれぞれの火種があり、抵抗運動の政治的イデオロギーは様々だったが、アジア主義という共通するグローバルなビジョンがあった。こうして「帝国主義の絶頂期にあった欧州列強に対抗するラディカル勢力「アジアン・アンダーグラウンド」が形成された。「欧米の主人たちと、支配されている自分たちの立場は逆転する」と確信するアジア主義思想は、最初に日本に拠点を見出すが、その後、共産主義の国際主義と重なりあい、最終的にはナショナリズムへ向かっていった。・・・。
-

文化は宿命である
Subscribers Only 公開論文
東洋の社会においては、個人が家族の延長線上に存在すると考えられている。個人は家族から分離した存在ではないし、一方では、家族も親類の一部、友人の環、より大きな社会の一部として存在する。
-

中国における大家族時代の終焉
中国の野望と人口動態トレンドSubscribers Only 公開論文
大家族の衰退という中国で進行するトレンドがいまや大きな流れを作り出している。この現象が引き起こす衝撃を北京が十分に認識していないだけに、家族構造の変化は、今後長期にわたって、中国の大国化願望を脅かし続けるだろう。1世代後の中国は、この人口動態上の逆風ゆえに、当局が想定するほど豊かでも生産的でもないはずだ。伝統的にライフボートの役目を果たしてきた大家族主義や血縁的つながりが衰退し、大規模な社会保障国家をあと1世代で構築しなければならないとすれば、経済外交と国防政策を通じて外国に影響力を与える北京の手段は大きく制約される。いずれ中国は経済パワーが低下し、国防政策を下方修正せざるを得ない状況に直面する。
中東秩序の再編とパワーゲーム
-

中東での壮大なパワーゲーム
核合意とイスラエル覇権の間雑誌掲載論文
イスラエルの軍事的成功、イラン系「抵抗の枢軸」の衰退とシリアにおけるアサド体制の崩壊が中東秩序を大きく揺るがした。ガザの占領拡大に加え、イスラエルはレバノン南部に自らの意思を押し付け、シリアの多くの地域に軍事侵攻した。そしていまや、イランを軍事攻撃することで、レバントでの勝利を湾岸にまで拡大したいと考えている。イスラエルが地域覇権を確立しつつあるかにみえたために、イスラエルとイラン間の新しいバランスを形作ろうと、湾岸諸国は、トランプが求める新たなイラン核合意を推進する主要なプレーヤーになった。そこでは、壮大な駆け引きが展開されていた。トランプは湾岸諸国の立場を優先し、イスラエルの意向を無視した。
-

イラン・イスラエル紛争のエスカレーションリスク
ドキュメント(6/13/2025)雑誌掲載論文
6月12日夜、イスラエルはイランに対する一連の大規模な攻撃を実施した。標的にはイランの核施設、ミサイル発射サイト、複数の軍・政治高官が含まれていた。イスラエルのネタニヤフ首相はテレビ演説で成功を宣言した。一方、イラン政府高官は復讐を誓い、地域の指導者たちは混乱に備えた。イスラエルの攻撃が意味するものをより深く理解するために、フォーリン・アフェアーズのシニア・エディター、ダニエル・ブロックがダニエル・B・シャピロに話を聞いた。シャピロは2025年1月まで中東担当の国防副次官補を務め、イスラエルとイランの緊張が全面戦争に発展した場合のシナリオを検討し、それに対応するアメリカの選択肢を準備するタスクを課されていた。
-

なぜイランは核兵器を保有すべきか
核の均衡と戦略環境の安定Subscribers Only 公開論文
現在のイラン危機の多くは、テヘランが核開発を試みているからではなく、イスラエルが核を保有していることに派生している。イスラエルの核保有のケースがきわめて特有なのは、核武装から長い時間が経過しているにも関わらず、依然として中東で戦略的な対抗バランスが形成されていないことだ。イスラエルは核開発を試みて戦略バランスを形成しようとするイラクやシリアを空爆し、これらの行動ゆえに、長期的には持続不可能な戦略的不均衡が維持されている。現在の緊張の高まりは、イランの核危機の初期段階というよりは、軍事バランスが回復されることによってのみ決着する、数十年におよぶ中東における核危機の最終段階とみなすことができる。現実には、イランの核武装化は最悪ではなく、最善のシナリオだ。この場合、中東の軍事バランスが回復され、戦略的均衡を実現できる見込みが最大限に高まる。
-

中東の危険な均衡
イランとイスラエルのパワーバランスSubscribers Only 公開論文
今後、イランとイスラエルの直接的な軍事衝突が常態化すれば、劇的な変化が生じ、そこにあるのは、ひどく不安定な均衡にすぎなくなる。直接攻撃の敷居が低くなれば、攻撃と報復の応酬が続き、中東でもっともパワフルな二国家が全面戦争、それも、アメリカも巻き込まれ、中東とグローバル経済に大きな悪影響を与えるかもしれない戦争に突入する危険は高くなる。一方で、弱体化したイランが核兵器を保有することで孤立の道を選び、その結果、核拡散潮流が生じる恐れもある。そのような未来を防ぐことが、ドナルド・トランプ次期米大統領の大きな課題になる。
-

イランの戦略目的は何か
混乱と変動から利益を引き出せる理由Subscribers Only 公開論文
テヘランは混乱のなかにチャンスをみいだしている。イランの指導者たちは、ガザ戦争を利用し、エスカレートさせることで、イスラエルを弱体化させてその正統性を失墜させ、アメリカの利益を損ない、地域秩序を自国に有利なものへ変化させようとしている。混沌とした状況から自国の利益を導き出すイランの能力を侮るべきではない。攻撃によってアメリカを刺激し、テヘランとその同盟国が有利になるようなミスを犯させたいとテヘランは考えている。だが、イランを含む関係勢力のいずれかが誤算を犯せば、中東全域でより激しい紛争が発生し、中東の安定とグローバル経済に大きなダメージが生じる恐れがある。
-

核をめぐるイランの立場
問題を作り出したトランプは何をすべきかSubscribers Only 公開論文
この2年にわたって、国連と国際原子力機関(IAEA)が、「イランが核合意で規定された条件を守っていること」を示す15の報告書を出してきたにもかかわらず、アメリカは経済制裁を再発動し、敵対的なレトリックでイランを攻撃している。イラン人は、合意を守らなかったのはアメリカで、イラン政府ではないと信じている。仮にテヘランが核合意や核不拡散条約(NPT)から離脱しても、最高指導者ハメネイのファトワ(宗教令)がイランの核開発を阻むことになる。2003年にハメネイは核兵器の所有と蓄積をファトワで公式に禁止している。イランとの交渉を望むと繰り返し発言しているトランプにその気があれば、最高指導者のファトワを基盤に包括的な合意をまとめる外交交渉の道は依然として残されている。
-

イランを内包する新中東秩序の構築を
中東の安定を取り戻すにはSubscribers Only 公開論文
中東を規定してきたこれまでのアラブ秩序は、この7年間の社会的混乱と内戦によってすでに引き裂かれている。ワシントンでは「イランの影響力を押し返せば中東に秩序を取り戻せる」と考えられているが、これは間違っている。むしろ、今後の持続可能な中東秩序にとって、イランが必要不可欠の存在であることを認識しなければならない。イランの対外行動が、イスラム革命の輸出ではなく、国益についての冷徹な計算によって導かれていることも理解すべきだ。現在の中東政策を続けても、イランの影響力を低下させることはなく、むしろ中東におけるロシアの影響力を拡大させるだけだ。紛争に終止符を打ち、平和と安定の枠組みを作るための地域合意を仲介するための国際外交に向けたリーダーシップを発揮しなければならない。この任務をロシアに任せるべきではない。
変化した朝鮮半島の地政学
-

トランプと金正恩
同盟国は悪辣な米朝取引に備えよ雑誌掲載論文
国際社会は北朝鮮の兵器開発・増強路線を止めさせることができず、いまや金正恩はこれまで以上に多くの交渉カードを持っている。当然、ワシントンのこれまでの北朝交渉モデルは選択肢にならない。条件を受け入れさせるには、大きな譲歩を示す必要がある。それは、北朝鮮を核保有国と認め、朝鮮半島から米軍を撤退させることを含む、同盟国に衝撃を与える内容になるかもしれない。ノーベル平和賞受賞への執着、ウクライナでの戦闘を終わらせたいという願望、そして金正恩に独特の友達意識をもつトランプは、北朝鮮の核保有を認め、同盟国を売り渡し、プーチンをなだめるような取引を、すべて「アメリカ・ファースト」の名の下に行うのかもしれない。
-
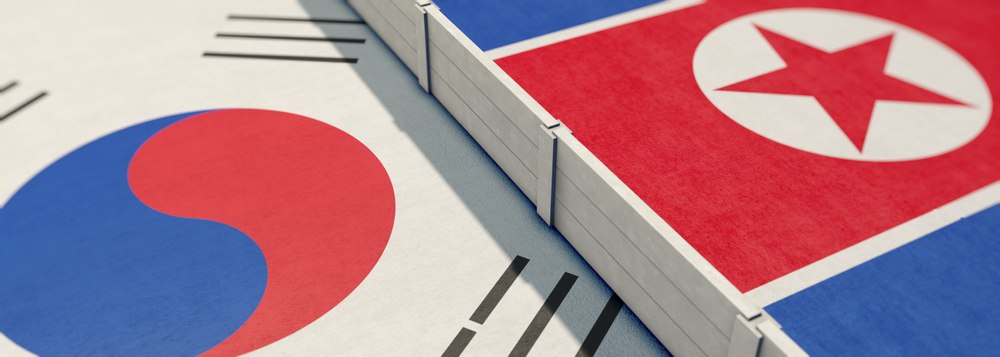
朝鮮半島のデタントを実現するには
変化した北朝鮮にどう向き合うか雑誌掲載論文
韓国が、北朝鮮との外交交渉を実現するには、「北朝鮮の完全非核化」や「朝鮮半島の統一」という非現実的なレトリック、そして「制裁を通じて北朝鮮の行動を変えられる」という幻想を放棄しなければならない。一方で、トランプの劇場型アプローチを李大統領の現実主義的なアプローチで補完する必要もある。金正恩は北朝鮮の経済問題と将来の繁栄をもっとも気にしている。半島統一という非現実的な展望を退け、北朝鮮の完全な非核化に固執するのをやめ、平壌に健全な経済発展への道筋を提示できれば、デタントの可能性は開けてくる。
-

ロシア・北朝鮮同盟と中国の立場
不安定な権威主義連合の行方Subscribers Only 公開論文
ロシアは平壌が長年望んできた高度な軍事技術を北朝鮮に売り渡すことを選んだ。中国がオファーしない利益をロシアが進んで提供してくれるために、平壌はモスクワに近づき、いまや北京は北朝鮮に対する手だての多くを失っている。一方、ロシアが北朝鮮に軍事支援を求めたという事実は、モスクワが北京から受けている物的援助がいかに少ないかを示している。実際、北朝鮮やロシアと連帯しているとみなされることのリスクを認識している北京は、むしろ、公の場では、この2カ国から距離を置こうとしている。中露・北朝鮮関係の歴史から現状を分析すれば、何がみえてくるか。
-

強大化した北朝鮮の核の脅威
平壌の核ドクトリンと韓国、東アジアSubscribers Only 公開論文
金正恩は、2022年9月に、核の「先制使用」ドクトリンを公表した。核兵器で米本土を脅かす力をもっているだけではない。北朝鮮の核は、北東アジアで軍拡競争を引き起こす危険がある。金正恩が突きつける脅威ゆえに、これまであり得ないと考えられていた核保有を求める韓国民衆の声は大きくなっている。だが、この流れが形成されれば、韓国が核開発を試みる前に、北朝鮮が韓国を攻撃するリスクは高くなる。日本も核武装に向かうかもしれない。問題は、北朝鮮の脅威が増大するなか、トランプ政権以降のアメリカの安全保障コミットメントが、かつてほど手堅くはないようにみえることだ。実際、北朝鮮の核攻撃によるアメリカの脆弱性が高まるなか、東アジアの同盟国がアメリカの「核の傘」に依存し続けられるかどうか、はっきりしない状況にある。
-

東アジアと中国の核戦力
核共有と軍備管理の間Subscribers Only 公開論文
中国の核戦力増強は、北朝鮮のそれと同様に、東アジアを変化させている。いまや韓国市民の多くが核保有を望んでいるし、日本の古くからの核アレルギーも緩んできている。アジアはいまや、秩序を不安定化させる軍拡競争に突入していく軌道にある。ワシントンは中国に対して、(軍備管理に関する)中身のある交渉に建設的に参加するか、あるいは、東アジアでアメリカが支援する核軍備の大規模な増強という事態に直面するか、という困難な状況にあることを理解させなければならない。中国の指導者たちが軍備管理交渉を拒否するようなら、ワシントンは(核保有国が同盟国と核兵器を共有する)核共有制度について、ソウルや東京と協議を開始することもできる。
-

韓国の核武装を認めよ
北朝鮮の脅威とアメリカの干渉Subscribers Only 公開論文
大陸間弾道ミサイルを開発した平壌は、いまや核兵器でアメリカの都市を攻撃する能力をもっている。このために、アメリカが(自国が反撃されるリスクを冒しても)韓国への安全保障コミットメントを果たすかどうかがいまや問われている。しかも、米韓同盟を批判してきたドナルド・トランプが大統領としての2期目を迎える。北朝鮮の核の兵器庫が拡大し、トランプ政権下のアメリカが後ろ盾としての信頼を失うにつれて、韓国の市民やエリートの核武装オプションへの支持は高まる一方だ。問題は、ワシントンが韓国の核武装路線に否定的なことだ。同盟国が危険にさらされたままの状態にあることを求めるのではなく、ワシントンは、ソウルが安全保障への道を自ら見つけることへの障害を取り払うべきだろう。
-

アメリカは同盟国を本当に守れるのか
拡大抑止を再強化するにはSubscribers Only 公開論文
尖閣諸島の防衛を約束しているとはいえ、中国は「価値のない岩の塊のためにアメリカが大国間戦争のリスクを冒すことはない」と考えているかもしれない。一方、ワシントンが信頼できる形で反撃すると約束しなければ、拡大抑止はその時点で崩壊し、尖閣の喪失以上に深刻な帰結に直面する。アメリカが何の反応も示さないことも許されない。これが「尖閣パラドックス」だ。今後の紛争は、大規模な報復攻撃を前提とする伝統的な抑止が限られた有効性しかもたない、こうしたグレーゾーンで起きる。中国とロシアの小規模な攻撃に対しては、むしろ、経済戦争、特に経済制裁を重視した対応を想定する必要がある。脅威の質が変化している以上、ワシントンは軍事力と経済制裁などの非軍事的制裁策を組み合わせた新しい抑止戦略の考案を迫られている。
Current Issues
-

それでも、ドルの覇権は続く
他に選択肢はない雑誌掲載論文
トランプ政権の関税策、そして彼がアメリカの法の支配に与えているダメージによって、2025年の成長見通しだけでなく、外国為替市場におけるドルの強さも脅かされている。1世紀以上にわたって準備通貨として君臨してきたドルも清算の時を迎えつつあるかにみえる。だが、有力な代替基軸通貨が存在しないために、今のところ米ドルがその地位から転落することはなさそうだ。実際、「ドル覇権の崩壊」という見通しは、他の主要通貨がドルに取って代わる機会を生かさなければ、実現しそうにない。他の準備通貨の脆弱性、経済・金融の混乱時における安全な金融資産への大きな需要があることを考えれば、ドル優位の時代の終わりを宣言するのは時期尚早かもしれない。
-
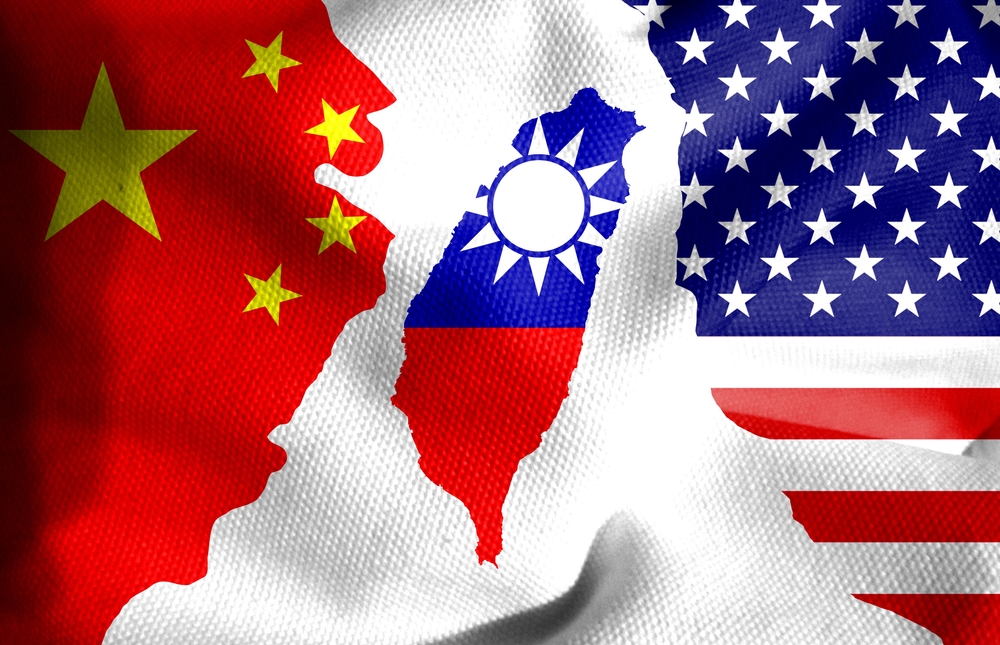
台湾侵攻を阻む抑止力の強化を
軍事・外交・経済の適切なバランスを雑誌掲載論文
中国の台湾侵攻を阻む抑止力を最大化するには、米台の防衛力を強化し、北京を安心させ、経済デカップリングなどの経済圧力策の行使を控えて軍事・外交・経済の適切なバランスをとる必要がある。問題は、これら三つをどのようなバランスで組み合わせるのが最適なのかに関するコンセンサスがほとんどないことだ。こうして、軍事力の強化は道半ばとなり、台湾に関する「戦略的曖昧さ」路線の揺らぎが北京の不安を高めている。その行使を控えることで、危機の際に抑止力を強化できるはずの経済圧力が、すでに高度に利用されている。軍事的即応態勢と軍事能力の強化に投資し、慎重な発言を心がけ、経済的なレジリエンスと一定の相互依存関係の維持に努めることが、台湾の安全強化につながる。
-

形骸化するアメリカの拡大抑止?
中ロによる切り崩し策雑誌掲載論文
中国の指導者たちにとって、アメリカの核の傘による拡大抑止は防衛戦略ではない。北京は「中国の台頭を封じ込め、後退させようと、ワシントンは、オーストラリア、日本、韓国など、北京からみれば、中国の勢力圏にある国に拡大抑止を押しつけている」とみている。概念面から拡大抑止を批判するだけではない。北京は、アメリカの軍事的役割を低下させ、米同盟国に対して軍事的・経済的威嚇策をとり、対米抑止力を強化し、ロシアとの協調を模索している。アメリカと地域同盟諸国が安全保障協力を強化しない限り、米拡大抑止戦略は今後、致命的に損なわれていくだろう。
-

新しい問題と古いアプローチ
政府の制度と役割をいかに見直すか雑誌掲載論文
危険と不透明性が高まっている時期に、市場で解決できない部分に介入し、人々を守り、変化を乗り切るのを助ける。これが、政府の役割だ。アメリカでは、所得格差、気候変動、AIによる社会再編など、先行き不透明感は高まっている。政府は、多くの人が「真の問題」と考えるものだけでなく、不確実な問題にも対処しようとしている。この過程で、指導者たちは、政府の機能を見直す必要に迫られる。これまでの進歩を維持し、先に進むのを妨げない柔軟な政府制度が必要になる。政府が時代遅れの手法をとり続ければ、現在の問題には対処できない。規制と規制緩和のバランスを見直すことも、経済活動や経済価値の実態を十分反映できる指標を考案する必要もある。







