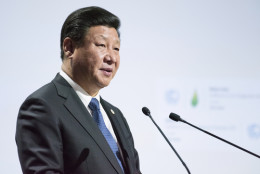ネパールの大いなる危機
――紛争のなかに取り残された民衆たち
2005年10月号

ネパール人の多くは、もうどうにもならないと感じている。毛沢東主義派に食料や隠れ家を提供することを拒むと「階級の敵」「反動分子」として処刑され、たとえ不本意であったとしても食料や隠れ家を提供すると今度はネパール国軍に毛沢東主義派との共謀の罪に問われる。国軍は、毛沢東主義派と、何とか生き延びようとしただけの民衆(同上)を区別できないし、区別しようとさえ試みない。いまやネパールは国家崩壊の瀬戸際まで追い込まれている。