ボストンテロと米ロ関係
――流れはボストンからチェチェン、そしてシリアへ
2013年04月

1994年以降に発表された邦訳論文を検索できます。
2013年04月

2013年4月号
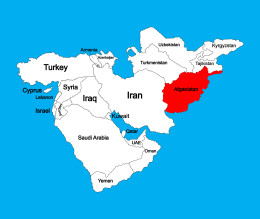
イラクという戦場は複雑だった。テロだけでなく、社会問題にもわれわれは直面していた。武装勢力がいただけでなく、宗派間抗争も起きていた。ネットワーク化された敵に対して、われわれもネットワーク化する必要があった。・・・「敵はどこにいるか」、「誰が敵なのか」、「敵は何をし、何をしようとしているか」を考えた挙げ句、結局「なぜ彼らはわれわれの敵なのか」を考えた。・・・アメリカにとっては、ドローン攻撃はリスクも痛みも少ないかもしれないが、攻撃される側にとっては、戦争であることに変わりはない。アメリカ人はこの点を理解する必要がある。現状で、そうした軍事技術をわれわれが無節操に用いているとは思わないが、そうなる危険は常に存在する。・・・武装勢力との戦争の重要なポイントは、たんに敵勢力を殺害することではなく、現地の民衆の面倒をみることだ。現地の民衆を守る積極的な理由があるし、そうしないのは間違っている」。(S・マクリスタル)
2013年04月

「北朝鮮が強硬路線を続けているのは、外からの脅威に屈すれば、国内的に面目を失うことを懸念しているからでもある。金正恩が確固たる国内基盤を築いていないために、ここで圧力に屈することは選択肢にならない。国内基盤を確立させない限り、平壌が現在のエスカレーション路線を緩和させることはないだろう。・・・われわれは、程度の違いこそあれ、同じパターンの北朝鮮の行動を何度も目にしているが、金正恩は、彼の父親よりもさらに大きなリスクを冒す戦術をとるつもりかもしれない。・・・ 平壌は、アメリカが北朝鮮のことを核保有国として認めることを望んでいる。韓国に対しては、朴槿恵政権が、前政権よりも平壌との安定した関係を望んでいるかどうかを、見極めたいと考えていると思う。・・・現状における大きな危険は、判断ミス、状況の誤認から衝突が起きてしまうことだ。・・・判断ミスによって深刻な事態に陥る危険がある。もう一つは、確たるエビデンスは存在しないが、国内の不安定化を前に北朝鮮が無茶な行動をとり始め、これが南北間の衝突につながっていく危険もある」

世界経済フォーラムの調査によれば、「極端な所得格差」と「長期間にわたる財政不均衡」の二つが、現状で専門家にもっとも注目されているグローバルリスクだ。これらは、大規模な政府債務の存在と悲観的な世界経済見通しへの人々の不安を映し出している。さらに、この1年で多くの国が異常気象を経験した結果、世界の指導者の多くが「温室効果ガス排出量の増大」を3番目のグローバルリスクとして認識している。そして、所得格差、財政不均衡、地球温暖化というリスクへの対応の鍵を握るのが、国や指導者のダイナミズムと柔軟性だ。指導者たちは、変化する環境に素早く適応するために必要な、大胆に発想して、行動する力をもっているだろうか。柔軟に問題に対応する国内環境を整備できているだろうか。われわれ(世界経済フォーラム)は、政治家の統治能力、健全な企業と政府の関係、改革の効率性、政治家に対する市民の信頼、政府による効率的な支出などが、国としての柔軟性を左右するとみている。
2015年3月号

アメリカの社会保障制度は、政府がすべての市民を対象とするのではなく、企業が従業員に提供する社会サービスに大きく依存している。このために、一部の所得レベルの高い人々は全般的に手厚い社会保障の対象とされるが、所得レベルが低いか、失業している人々はそうではない。他の豊かな民主主義国と比べて、アメリカの社会保障政策による貧困と格差緩和への貢献度が低いのは、このためだ。他の多くの先進国では、官民の社会保障プログラム、減税策を組み合わせて、社会保障がより平等かつ効率的に提供されている。アメリカとの最大の違いは、他の先進国のシステムは平等と効率を目的にし、広く市民が社会保障にアクセスできるように設計されていることだ。当然、アメリカの社会保障制度の改革に向けて、こうした他の先進国のモデルを真剣に検証する必要がある。

ユーロ圏からのギリシャ離脱というシナリオが、いまやEUからのイギリス脱退というシナリオに置き換えられている。イギリスではEUに対する不信がかつてなく高まっている。EUが(ユーロを救うために)経済・政治同盟の統合を進化させるための措置を導入していくにつれて、ユーロゾーンの中核国と、統合の深化に歩調を合わせるのを嫌がっているユーロに参加していない国の間の亀裂は必然的に大きくなっていく。ヨーロッパはユーロを救うために、欧州連合を分割すべきなのか。・・・

イスラエルは、アサド政権が倒れた後に、イスラム主義政権、それもジハード主義政権がシリアに誕生することを警戒している。政権崩壊によってシリアが混沌とした状況に陥れば、ジハーディストがゴラン高原からイスラエルに対してテロ攻撃を試みるかもしれない。あるいは、イスラム主義政権がシリアの化学兵器や生物兵器をヒズボラに与えるか、そうした兵器を過激派勢力が混乱に乗じて手に入れる危険もある。さらには追い込まれたアサド政権が、道連れとばかりに、イスラエルに向かってミサイルを発射するリスクもある。より全般的には、イスラエルは、アサド政権とその同盟勢力がシリア内戦をイスラエルとの戦争、アラブ・イスラエル紛争へと変貌させることを警戒している。エルサレムは公的な声明を通じて、どのような事態になれば介入に踏み切るか、イスラエルにとって看過できないレッドラインを明確に示してきた。最先端の兵器システムがヒズボラの手に落ちることもレッドラインの一つだった。今回のイスラエルによるシリア空爆は、この文脈で理解されるべきだ。問題は、空爆によって抑止力が形成されたかどうかが、はっきりしないことだ。
2013年3月号

シリアでアサド政権が追い込まれていくにつれて、ヒズボラは、シリアにある自分たちの兵器を、レバノン山岳地帯の洞窟に設けた兵器庫など、安全な場所に移したいと考えている。イスラエルが空爆で攻撃したのは、そうした兵器を積んでレバノンに運びだそうとしていたトラック車列だった。スンニ派の過激派、シーア派の過激派は、アサド体制の崩壊に備えて、それぞれ自分たちに忠実な武装勢力の組織化を進めている。われわれが目にしているのは、紛争の第2局面に向けた兵器の備蓄・調達に他ならない。さらに、イランがヒズボラへの武器提供をシリア経由で行うことが多いことも、今回の空爆の構図に関係している。現状ではヒズボラとイランは非常に緊密な関係にあり、アメリカの情報コミュニティは、両者の関係を「戦略的パートナーシップ」と描写している。
2013年3月号
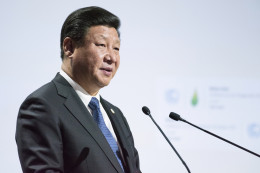
「日本との紛争で自国が敗れ去る」とは北京は考えていないが、「いかに圧倒的な軍事的勝利を収めても、武力行使は副作用が大きすぎる」とみている。武力衝突という事態になれば、経済成長を維持し、国内のナショナリズムの激化を抑えるという、北京にとってきわめて重要な二つの基本的国益に悪影響が出るからだ。いかなる抑止力にも増して、こうした国内的な自制要因ゆえに、習近平が、尖閣をめぐって武力行使を認めることはないだろう。もちろん、北京が「気晴らしの戦争が自分たちの権力を維持する唯一の方法だ」と考える危険もある。だが、戦争によって誰も勝者になれないことを理解すれば、中国は日本に対する瀬戸際作戦を回避するはずだ。
2013年3月号

ユーロ危機の打開に向けた財政同盟、銀行同盟のためのビジョンが描かれ、欧州中央銀行(ECB)が最後の貸し手の役目を果たす態勢も整いつつある。しかし、ヨーロッパの政治が大きな障害を作り出している。いまやベルリンは独自路線をとり、一方のパリは内向きになっている。・・・ユーロの安定化に向けてドイツが示した(財政同盟などの)処方箋は統合の深化を必要とする。国家主権を譲ることについて連邦制のドイツはそれを問題と感じないが、歴史的に国家主権にこだわってきたフランスはそうではない。今後、危機対応をめぐって独仏の立場の違いが先鋭化してくるのは避けられないだろう。一方、キャメロン英首相は、イギリスとEUとの関係を再交渉し、少なくとも、EUから距離を置きたいと考えている。そうした緩やかな関係であれば、市民の支持をとりつけて、イギリスは今後もEUに関わり続けることができるようになると考えているからだ。だが、その結果、イギリスの地政学的重要性が低下する危険があるし、一方ではスコットランドの独立というリスクもロンドンは抱え込んでいる。・・・