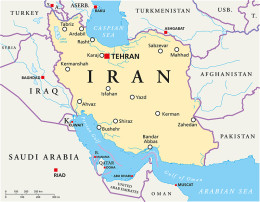二〇〇一年九月の米同時多発テロ事件以降、サウジアラビアとアメリカの関係は政治的に微妙となり、流動化している。加えて、アメリカのサダム・フセイン追放作戦をめぐる米・サウジアラビア関係のきしみも取りざたされる。こうしたなか、世界でクローズアップされているのは、イラク侵攻後の中東情勢、サダム後のイラク再建、さらには、石油の価格と安定供給がどうなり、それが世界経済にどのような影響を与えるのか、シーレーン防衛が見直されることになるのか、そして、これらが世界の安全保障地図にどのような影響を与えるのか、という大きな問題だ。これらのすべてにおいて、サウジアラビアが重要な鍵を握っている。
「テロ後の世界が、ロシア、アメリカ、石油輸出国機構(OPEC)にとって、まったく新たな地政学の見取り図をつくり出していること」を踏まえた戦略をとることの必要性を説いた「石油をめぐるロシア対サウジの最終決戦」(The Battle for Energy Dominance, Edward L. Morse, James Richard, Foreign Affairs 2002 March/April,「論座」二〇〇二年五月号)は、世界で、また石油の九九・七%を輸入に依存する日本でも大きな話題となった。論文の筆者であるエドワード・L・モースとジェームズ・リチャードは、ロシア政府がテロ後の「エネルギーをめぐる新たな地政学状況を政治・経済的に立ち直る好機」ととらえていること、ロシアの石油企業が国際化、市場経済化しつつあることに注目し、ロシアとカスピ海周辺地域などの旧ソビエト地域における市場経済型の石油開発計画が実現すれば、「今後四年のうちに旧ソビエト諸国からの石油輸出の合計は、サウジアラビアの輸出にほぼ匹敵する規模になる」と指摘した。ここに掲載するのは、「石油をめぐるロシア・ファクターを考慮した、テロ後の石油戦略及び地政学の見直しの必要性」を説いた同論文に対する反論と、筆者たちによる再反論。