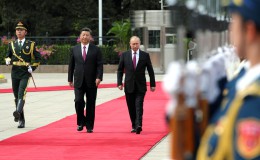分裂した世界とグローバルな脅威
―― パンデミック・気候変動と大国間競争
2021年10月号

この100年で最悪のパンデミックはいまも収束していない。気候変動危機も加速する一方だ。しかも、大国間競争という環境下で、ワシントンはこれらのトランスナショナルな脅威に対処していく戦略を考案していかなければならない。米中のライバル関係は熱い戦争は引き起こしていないが、冷たい戦争に火をつけかねない状況にある。だが、未来のパンデミックに備え、気候変動と闘うには、ライバル諸国、特に中国との協調を模索しなければならない。だが一方で、協調路線が破綻した場合に備える必要もある。同盟諸国とパートナー諸国が、グローバルな公共財のためにより大きな貢献をするバックアッププランも用意しておくべきだろう。2020年には存在しなかったそうした計画を、次の危機までに間違いなく準備しておかなければならない。