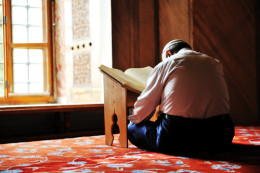北朝鮮が核を開発し、イランが核開発の道を歩んでいるにも関わらず、多くの人は世界の核秩序は安定していると考えている。たしかに、核保有国の数は9カ国に留まっているし、今後、北朝鮮とイランが核保有国と見なされるような事態にならなければ、近い将来に核拡散の潮流が生じて、数多くの国が核武装すると危機感を抱く必要はないと考えることもできるだろう。だが現実には、核不拡散レジームの形骸化が進み、一気に核が拡散してしまう、取り返しのつかない臨界点へと近づきつつある。盗み出された核によってテロが起きる危険もある。核秩序を守るための措置はすでに表明されているが、国際社会がそうした措置を現実に実行していかなければ、世界は一気に核拡散の大潮流に席巻される危険がある。今後の一年は非常に重要であり、各国が行動を起こすべきタイミングはいまだ。核不拡散レジームが崩壊したら、もはや手の打ちようはないのだから。