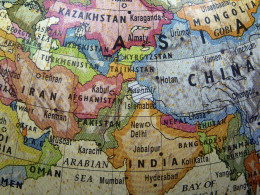イスラエルが近くヒズボラを攻撃し、第3次レバノン戦争が起きる危険がある。ヒズボラが保有するミサイルの備蓄規模が大きくなり、その攻撃精度も高まっている。しかも、攻撃精度の高い長距離ミサイルをシリアから入手し、地対空ミサイルの能力を向上させている可能性もある。これら三つの要因が伴う戦略バランスの変化ゆえに、イスラエルは自国の安全保障が脅威にさらされていると判断するかもしれないからだ。もっとも可能性が高いのは、イスラエルが、ヒズボラの長距離ミサイルを搭載した移動用コンボイ、レバノンにあるロケットやミサイルの兵器庫を攻撃することだ。国際社会はこの現実にどう対処すべきなのか。ヒズボラのパトロンと言われるシリアとイランはどう動くのか。