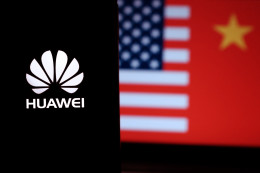絶望死という疫病?
―― アメリカ特有の現象か、グローバル化するか
2020年3月号

アメリカの平均寿命が低下し始めた大きな理由は、25歳から64歳の中年の死亡率が上昇しているからだ。ドラッグのオーバードーズ(過剰摂取)やアルコール性の肝臓疾患による死亡、そして自殺が増えている。これらの3タイプの絶望死のなかでオーバードーズがもっとも多く、2017年に7万人が犠牲になり、2000年以降の累計では犠牲者数は70万を超えている。厄介なのは、他の諸国もこのアメリカのトレンドの後追いをすることになるかもしれないことだ。他の富裕国の労働者階級もグローバル化、アウトソーシング、オートメーションが引き起こす経済的帰結に直面している。エリートが繁栄を手にし、教育レベルの低い人々が取り残されるという、アメリカの絶望死危機を深刻にしているダイナミクスが、他の富裕国でも壊滅的な結果をもたらす恐れがある。