インドはアメリカの戦略的パートナーだ
――米印核合意の本当の目的
2006年8月号
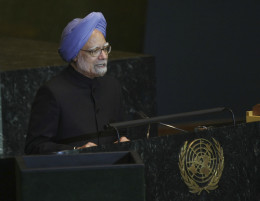
ワシントンが核の平和利用をめぐってインドに譲歩したのは、別の領域でもっと多くのものを勝ち取るためだった。イランの脅威、政情不安定なパキスタン、そしてとかく行動が読めない中国などの国々が将来引き起こすであろう課題に対処していくうえで、戦略的な要地に位置し、めざましい経済成長を遂げる民主国家インドの支援と協力を確保することをワシントンは重視した。核保有国としての地位を認めることと引き換えに、インドを戦略的パートナーとして取り込むという取引は、アメリカにとって妥当な決断だった。この合意が成功するかどうかは、ひとえにインドの将来の行動にかかっている。









