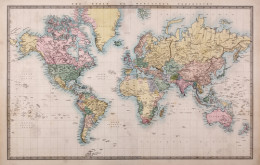1930年代初頭、毛が引き継いだ共産党は衰退途上にあった。事実、1937年に日本が中国を侵略するまで、共産党は中国政治ではまったく目立たない存在だった。しかしその後共産党は、中国北方における愛国主義運動の指導的役割を担うようになった。外国の専門家が彼らを愛国主義者と呼んだのは間違いではなかった。外国の侵略者が家屋に火を放ち、虐殺行為を行っているさなかに、農民を組織するのは簡単ではなかったが、日本軍の行動が、結果的には中国北部の農民を中国共産党の懐へと送り込んだ。共産党側は準備万端調えて、農民が自分たちのところへ転がり込んでくるのを待っていればよかった。重要なポイントは、あえて地主階級への反対を前面に出すより、むしろ抗日戦への愛国主義を訴えるほうが、国内の青年知識層が呼びかけに応じる可能性が高いことを共産主義勢力が理解していたことだ。