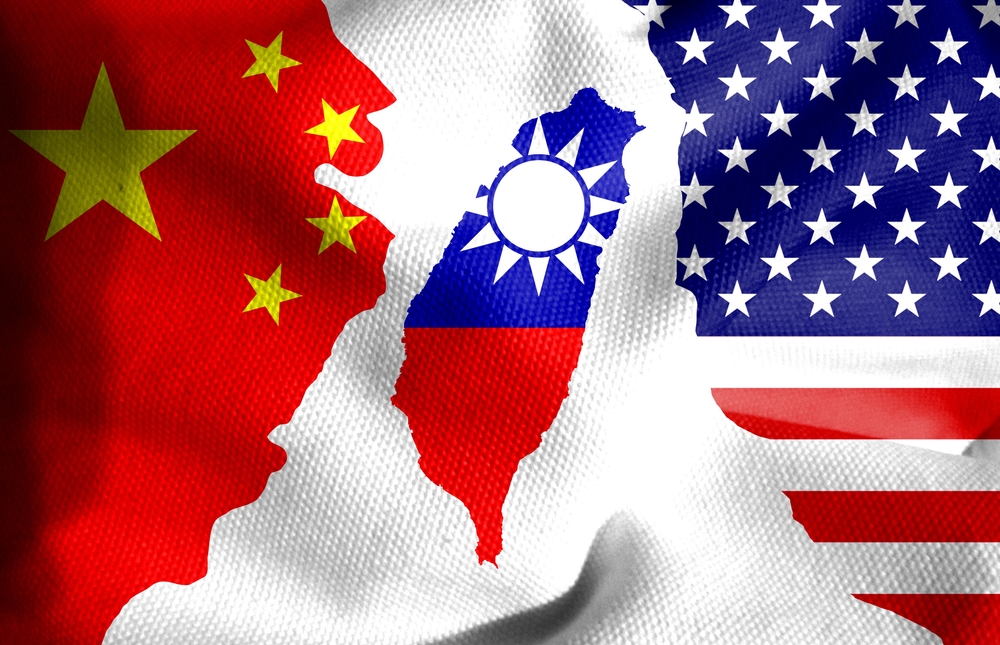 Andy.LIU / Shutterstock.com
Andy.LIU / Shutterstock.com
台湾侵攻を阻む抑止力の強化を
―― 軍事・外交・経済の適切なバランスを
The Taiwan Tightrope: Deterrence Is a Balancing Act, and America Is Starting to Slip
2025年7月号掲載論文
中国の台湾侵攻を阻む抑止力を最大化するには、米台の防衛力を強化し、北京を安心させ、経済デカップリングなどの経済圧力策の行使を控えて軍事・外交・経済の適切なバランスをとる必要がある。問題は、これら三つをどのようなバランスで組み合わせるのが最適なのかに関するコンセンサスがほとんどないことだ。こうして、軍事力の強化は道半ばとなり、台湾に関する「戦略的曖昧さ」路線の揺らぎが北京の不安を高めている。その行使を控えることで、危機の際に抑止力を強化できるはずの経済圧力が、すでに高度に利用されている。軍事的即応態勢と軍事能力の強化に投資し、慎重な発言を心がけ、経済的なレジリエンスと一定の相互依存関係の維持に努めることが、台湾の安全強化につながる。
- 台湾戦略のバランス
- 戦力強化のバランス
- 北京を安心させるには
- 貿易戦争から軍事戦争へ
<台湾戦略のバランス>
台湾海峡の緊張が高まるなかにあっても、ワシントンの政策論争は依然として分裂したままだ。中国による台湾侵攻の抑止を目的とする最近の米三政権の戦略は、(1)米台の防衛能力を強化し、(2)台湾防衛へのワシントンの決意を示す一方で、台湾の独立を支持しないことを北京に伝えて安心させ、(3)中国の軍事的近代化の試みをスローダウンさせるために経済圧力を行使するという支柱で構成されていた。
問題は、これら三つをどのようなバランスで組み合わせるのが最適なのかについての、コンセンサスがほとんどないことだ。実際には、抑止戦略がどのようなものになるかはこのバランスに左右される。「軍事的に自制し、中国を刺激するのを避ければ、外交的圧力によって、北京の行動を瀬戸際で抑え込める」とする考えの一方で、「アジアにおける軍事態勢(能力)を大幅に強化しなければ、抑止は崩壊する」という意見もある。第3のアプローチとして、ジェニファー・キャバナーとスティーブン・ワートハイムがこの雑誌で最近提示したのが「台湾の自衛力を高め、アメリカはオフショア支援に徹する」という路線だ。2人は、これが抑止を維持し、エスカレーションリスクを緩和する最善の道筋だと提言した。(「東アジアと台湾を捉え直す―― 中国のアジア覇権を阻むには」 FAR2025年5月号)
これらの主張にはそれぞれ利点はあるが、米戦略の中核に存在するパラドックスにはうまく対処できない。抑止は二つのケースで破綻する危険がある。まず、抑止が不十分だと「北京はワシントンが動き出す前に台湾を攻略できる」と考え、賭けに出るかもしれない。そして、抑止力が過剰な場合も、北京は(もはや外交や経済ツールでは対処できないと判断し)武力行使が統一に残された唯一の道だと考えるかもしれない。
このジレンマを克服するには、軍事力の強化や大胆な外交以上のものが必要になる。弱腰にも無謀にもならないように、軍備増強・安心の供与・自制の三つを細かに組み合わせた戦略が必要になる。(軍事的な)前方展開戦力、外交的抑制、選択的な経済的相互依存を適切に組み合わせれば、互いに補完し合い、挑発を避けつつも信頼に足る抑止力を維持できるようになるだろう。
しかし、これまでのところ、トランプ政権の台湾に対するアプローチは、4月に台湾製品の多くに対して32%の関税を課すなどの「乱暴な取引主義」と、超党派議員団の台湾訪問や関税の最高税率の一時停止などの「台北への静かな支持表明」の間を揺れ動いている。トランプ政権が、一貫した戦略に落ち着くための時間はまだ残されているが、その機会は次第に閉ざされつつある。
<戦力強化のバランス>
現在、米軍は台湾周辺における戦力の再編と強化に取り組み、フィリピンの基地へのアクセスを強化し、日本南西部や広く西太平洋での戦力強化を試みている。フィリピンでは、防衛協力強化協定(EDCA)を通じて、新たに4カ所の戦略拠点へのアクセスを確保し、これで米軍の拠点は合計9カ所に増加した(カガヤン州、イサベラ州などにおける拠点は台湾から数百マイルしか離れていない)。
日本も似たような状況だ。日米は2023年、沖縄に駐留する米海兵隊戦力を再編することに合意した。これによって、沖縄に駐留する米海兵隊1万8000人の一部として、砲兵隊を中心とする第12海兵連隊は約2000人規模の海兵沿岸連隊に改編される。目的は、インドネシア、日本、フィリピンの一部、台湾を含む「第1列島線」に即して迅速に展開できる「緊急対応部隊」として活動させることにある。この試みを補完するために、米軍は合同軍事演習を増やし、同盟地域で統合型の防空・ミサイル防衛システムの導入拡大をすすめている。
しかし、太平洋地域における米軍事力強化には、単なる量的アップグレード以上のものが必要だ、中国の武力による台湾攻略を阻止するには、質的なシフトも必要になる。より大きな前方展開戦力が必要だし、戦略爆撃機、潜水艦、対艦ミサイルなどの、中国の侵略軍が海峡を通過して台湾に上陸するのを阻止する具体的な戦力が必要になる。これらの戦力を配備した上で、作戦面での高度な柔軟性が求められる。たとえば、ワシントンは、潜水艦がグアムやハワイに戻らずに再装填・補給・再武装ができるように、日本やフィリピンから(潜水艦に補給を提供する)潜水母艦の事前配備の合意を取り付けることを優先すべきだろう。さらに、オーストラリアとフィリピンに爆撃機のための基地を確保し、日本の南西諸島およびフィリピン北部に対艦ミサイルシステムを配備できるように努めるべきだ。
これまで米軍は、政治的に微妙な内外の問題に関わってくるために、こうした変化を積極的には推進してこなかった。ホスト国は、中国の攻撃対象にされるリスクが高まることを懸念するし、米高官のなかにも、こうした措置が、北京にとっての「レッドライン」を越えるのではないかと心配する者がいる。しかし、一定の原則を守れれば、そうした戦力やプレゼンスの見直しが、必ずしも中国の攻撃を誘発するわけではないだろう。
第1に、アメリカは戦略の強化を公に発表したり、大げさに取り上げたりすべきではない。合同演習、航行の自由作戦、軍事訓練など、米軍が台湾周辺や台湾での活動を強化する場合には、「中国側が対応を示さざるを得ないと感じるような発言」は控えるべきだ。軍事的なアップグレードは、配備が完了するまで水面下ですすめるか、控えめに実施し、中国がそうした配備を理由に強制的な手段に出る可能性を最小限に抑えなければならない。
台湾の軍事能力を強化するというワシントンの長年の政策は、中国を挑発するさらに大きなリスクがある。北京は「台湾が自衛能力への自信を深めれば、独立宣言に踏み切るのではないか」と懸念している。近年、台湾は中国による侵攻を抑止する目的で、防衛能力の強化をすすめてきた。たとえば、沿岸防衛巡航ミサイルやHIMARSロケット砲システムなどの(軍事力に大きな格差がある相手を想定した)非対称戦争のためのシステムを導入し、潜水艦などの高コストな従来型装備からの転換を促している。
2025年には、国防予算を域内総生産(GDP)比で3%超に引き上げ、精密誘導兵器、防空システム、指揮統制システム、予備役装備、対ドローン技術などの増強を重視すると約束している。これらは合理的な措置だが、同時にリスクも抱えている。台湾がアメリカの支援への依存を低下させれば、北京は、頼清徳台湾総統が一方的に独立を宣言する可能性を憂慮するようになり、早い段階で台湾侵攻を決断する動機を高めてしまいかねない。
抑止の試みが挑発とみなされるのを防ぐために、ワシントンは「アメリカの支援に依存せざるを得ない軍事能力」を台湾へ供与すべきだろう。2024年、バイデン政権は、米台間の相互運用性を高めるために、3基のNASAMS(中高度防空ミサイル・システム)の台湾への売却を承認した。このシステムは米軍との共同作戦でもっともうまく機能する。
もちろん、アメリカは台湾の非対称戦防衛力を引き続き支援すべきだし、特に、高度な可動性と精密性を兼ね備えたHIMARS、NASAMSのような先端防空ミサイルシステム、そしてRGM−84L−4ブロックⅡ型ハープーンのような対艦ミサイルなどの迅速かつ確実な供給を優先すべきだ。だが、台湾の軍事力がアメリカの能力に依存していることを明確にし、台湾が独自に行動できるわけではないことを北京にはっきりと示す必要もある。
<北京を安心させるには>
北京を安心させることも、抑止戦略を成功させる重要な要素だ。しかし、(第1次)トランプ政権もバイデン政権も、長年維持してきた(ワシントンが台湾防衛に介入するかどうか、その条件が何かを意図的に曖昧にする)「戦略的曖昧さ」を緩めてきた。ワシントンは台湾を防衛する意思を中国に伝えるようになり、米台双方の高官レベルの交流など、台湾との正式な外交関係に近づく段階的な措置をとることで、北京にメッセージを送ってきた。
実際、ジョー・バイデンは、台湾の外交代表を米大統領就任式に招いた初めての大統領になった。台湾防衛へのアメリカの「コミットメント」を繰り返し、「前例のない攻撃」があった場合には米軍が台湾を防衛すると一度は明言した(当時のホワイトハウスの高官は、「戦略的曖昧さ」の政府方針に変更はないと説明することで対応した)。第2次トランプ政権のマイク・ウォルツ大統領補佐官(当時)を含む高官の一部も、「戦略的曖昧さ」を終わらせ、「戦略的明確さ」へと移行すべきだと主張してきた。2025年2月には、国務省のウェブサイトから「台湾独立を支持しない」との文言が削除され、中国はこれを挑発的な動きとみなした。
これはシンボリックなものにすぎないように思えるが、このような外交的に軽微なケースも、北京にとって「台湾との統一に向けた進展」という体裁を保つことが難しくなれば、重大な意味を伴う。北京は、台湾独立へのいかなる動きも、自らの正統性を脅かす脅威とみなしている。このために、米台間の公的な外交接触、台湾を「国家」と呼ぶこと、あるいは、米台同盟締結の提言などの挑発行為は、北京を抑止するどころか、むしろ台湾海峡を越えた侵攻を促すことになる。
ワシントンが台湾の独立を支持しないことを中国に再確認させるには、台湾の指導者が独立を示唆するような言動をとった際には、公的に批判しなければならない。たとえば2003年12月、ジョージ・W・ブッシュ大統領は、中国の温家宝首相との共同記者会見で、アメリカは「中国あるいは台湾のいずれかによる現状変更の一方的決定」に反対すると明言し、台湾の陳水扁総統(当時)の「発言と行動」は、「現状変更を一方的に決断する意思があることを示している」と批判した。
2006年に陳が、中国との統一の道筋を示すために設置されていた政府関連組織「国家統一委員会」を廃止し、北京を刺激すると、ブッシュ政権は、ラテンアメリカ歴訪の途上で陳総統がアメリカに立ち寄る計画を拒否することで、独立の不支持を明確にした。このように中国を安心させる姿勢は、「将来の平和的統一」が依然として可能だとの立場を北京が維持し、武力侵攻の可能性を引き下げる効果がある。
アメリカは、台湾海峡の平和に向けた多国間コンセンサスの形成も引き続き模索すべきだ。たとえば、2024年のG7外相会議やミュンヘン安全保障会議で発表された共同声明では、台湾海峡の安定が改めて確認され、武力や威圧を含む一方的な現状変更に反対する姿勢が示された。ワシントンはこうした外交的なシグナルに加え、「一つの中国」政策が依然として有効であること、いかなる解決策も平和的なものでなければならないこと、そして台湾の同意がある場合の平和的統一に反対しないことを、はっきりと再確認すべきだろう。
<貿易戦争から軍事戦争へ>
軍事力や外交姿勢の見直しに比べて、米抑止戦略における第3の要因である経済圧力路線の見直しはより困難かもしれない。(関税策、経済デカップリングなどの)経済圧力の行使は、抑止と(中国への)安心供与をともに損なう恐れがある。第1次トランプ政権以降、ワシントンは対中経済封じ込め戦略を模索している。長期的成長を鈍化させ、先端技術へのアクセスを遮断することで、中国がアメリカの軍事投資に匹敵する能力を獲得するのを阻止しようとしてきた。
この路線は、数十億ドル規模の中国製品を対象とする第1次トランプ政権による関税策から始まった。バイデン政権はこれを維持しただけでなく、半導体や通信機器などの戦略的に重要な技術を輸出規制の対象に加えた。さらに、米企業がサプライチェーンや製造拠点を中国からシフトさせる(リショアリングする)ように圧力をかけた。
第2次トランプ政権は、無条件かつ広範な関税によって、経済デカップリングをさらに加速させると中国に迫っている(もっとも、デカップリングによってアメリカも経済的痛みを強いられるために、現状では様子見をしているようだ)。とはいえ、こうした封じ込め策は、人口動態や環境面での課題に直面している中国経済に、永続的なダメージを与えるかもしれない。ワシントンは、中国の経済成長率が鈍化し、北京が軍備拡張のペースを維持できなくなることを期待している。
しかし、現在進行中の米中貿易戦争と、エスカレートするアメリカの輸出・投資規制は、北京の不信感をさらに高め、「ワシントンは平和的共存ではなく、封じ込めを求めている」という主張を強めている。こうした経済圧力は、中国の決意を頑なにするリスクがあるだけでなく、北京が「世界の貿易ルールの擁護者」という立場へ乗り換えることを許し、世界経済の減速に対する責任をアメリカに転嫁する口実を与えることになる。
同時に、アメリカが(中国に対する)長期的な手立てを失うリスクもある。関税策によって、中国共産党(CCP)が掲げる「内需拡大」、つまり輸出ではなく国内市場で製品の販売を拡大させることへのコミットメントが一層強化されるかもしれないからだ。そうした経済構造の転換は、中国内における生産とイノベーションを促し、外国市場への依存を減らす流れを加速させるだろう。
こうしたアメリカの戦略は、中国の長期的な軍事力には限定的な作用しかしない。中国は歴史的に低コストで軍事力の近代化をすすめ、「大砲かバターか」という古典的ジレンマに直面するのを回避してきた。かつての大国間競争とは違って、中国はアメリカの国防支出と予算で競い合うような動きもみせていない(ナチス・ドイツは、1933―39年に、イギリスの2倍の予算を国防に投じた。冷戦期の米ソの国防予算は、はっきりとした競争関係にあった。アメリカの予算は1970年までソビエトを平均32%上回っていたが、その後はソビエトが逆転し、1988年までアメリカを平均26%上回る国防費を投入した)。
これに対して中国は、限定的予算で、短期戦争で優位に立つための的確な投資を実施することで、全般的な国防支出の増大を抑えてきた。1995年にはアメリカの5%にすぎなかった国防支出が、2017年に32%へ上昇した程度だ。要するに、中国は、経済発展と軍の近代化の両立を実現しつつ、冷戦型の軍拡競争を回避してきた。もちろん、経済が停滞しても、GDPに占める軍事支出の割合を高めれば、軍の近代化路線を今後も維持できる。
実際のところ、貿易戦争は中国を抑止するどころか、武力衝突をより魅力的にみせる可能性がある。現状で、台湾侵攻を北京が検討するのは、米軍が介入する前に台湾を制圧できるとみなす、限られたシナリオにおいてだけだろう。中国にとって、大規模で長期的な戦争は代償が大きすぎる。米中経済関係がもつ価値の大きさも、この判断に関わってくる。だが、ワシントンが経済的圧力をさらに強化すれば、北京にとって、対米経済エンゲージメントを維持するメリットは小さくなり、むしろ、アメリカの影響から抜け出す唯一の道は武力衝突だと考えるかもしれない。この場合、台湾をめぐる戦争への敷居は低くなる。
経済的、外交的譲歩を通じて、現状を維持することへの中国側の利益認識を高め、ワシントンの意図が敵対的ではないと信頼性をもって伝えられれば、中国側を安心させられる。まず、経済デカップリングを停止または撤回すべきだろう。ワシントンは(少なくとも相応の見返りを条件に)中国製品に対する関税を撤廃すべきだし、センシティブな技術や分野を除いて、輸出や対米投資への規制を緩和する必要がある。こうした措置をとれば、「アメリカは中国を弱体化させ分断しようとしている」とみなす北京の脅威認識を緩和できるだけでなく、国内不安定化の余波を低下させることができる(不安定化は共産党の正統性を脅かし、ナショナリスティックな正統性を強化するために台湾への武力侵攻を促す危険がある)。
だが重要なのは、経済的相互依存、特に現在のような非対称の相互依存を維持することで、アメリカは中国に対して極めて大きな影響力を維持できることだ。仮に戦争となった場合、アメリカの制裁だけで、中国経済を永続的な衰退軌道に向かわせられるかもしれない。つまり、経済デカップリングを一時停止または制限すれば、経済制裁の威力を(未来に向けて)最大化して抑止を強化できる。
もちろん、経済的相互依存を強化するには、一方で、レアアース、送電網用変圧器、希少な医薬品(原薬)、ハイテク電子機器、その他の産業・インフラ・軍事関連資材など、中国からの主要輸入品への依存を低下させることも必要だ。アメリカはこれらの物資の調達先を多様化し、中国からの輸入比率を許容できる水準まで引き下げるべきだろう。一方で、簡単に代替できる中国の消費財は、現時点で輸入を即座に抑え込む必要はない。こうした消費財の輸入を維持することで、中国経済の不安定化を避けつつ、中国にダメージを与えられる制裁ツールを温存できる。そして最後に、中国に対する抑止力を最大限に高めるには、同盟国と連携した制裁枠組みを構築すべきであり、そのためには同盟国に支援を提供し、譲歩する必要があるかもしれない。
ワシントンの多くの人は、抑止のことを、中国に対して妥協を許さず、敵対的な姿勢をとることだと考えている。しかし、こうした態度が台湾の安全を実質的に高めることはない。むしろアメリカは、軍の即応態勢と能力強化へ投資し、慎重に発言し、経済的なレジリエンスと一定の相互依存関係の維持に努めるべきだ。
抑止は、挑発にエスカレートし、一方では問題の先送りにつながりやすいというジレンマを伴うだけに、綱渡りのように慎重なアプローチが必要になる。そして、このバランスをうまくとることで、大きな成果をもたらせる地域があるとすれば、それがまさしく台湾だろう。●
(C) Copyright 2025 by the Council on Foreign Relations, Inc., and Foreign Affairs, Japan




