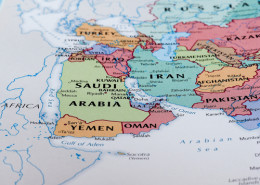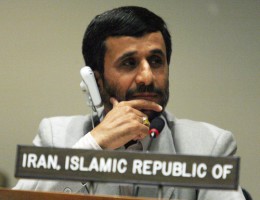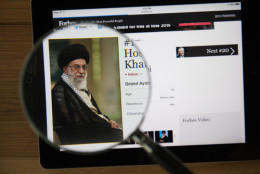原油価格高騰の真相
2006年4月号

悲観論者たちは、世界の資源はすでに開発し尽くされており、原油価格のダイナミクスや技術の発展も石油資源の「限界」を覆すことはできないと考えている。たしかに石油の消費が増加の一途をたどっている以上、既存の石油資源に関しては必然的に枯渇に近づいている。だが、科学を装った「資源枯渇」という悲観論者の宿命論は、これまで幾度となく間違っていたことが実証されている。この20年にわたって石油関連投資がないがしろにされてきた結果の原油不足に、中国などの需要増が追い打ちをかけているというのが真実に他ならない。石油資源は潤沢にあるし、今回の原油高騰を例外的な現象とみなすのは間違っている。