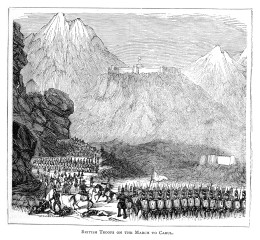モスクワが自国のエネルギー資源を外交ツールとして用い、国内のエネルギー産業への支配体制を再度強化しようとしていることに、諸外国は警戒を強めている。ごく最近も、220億ドル規模のサハリン2プロジェクトの経営権を、合弁プロジェクトに参加している外資企業3社から政府系の天然ガス独占企業であるガスプロムに移動させるという強引な行動に出ている。また、ベラルーシ、ウクライナ、グルジアなどの近隣国に対して、強引に天然ガスの供給価格の引き上げを受け入れさせようとするロシアの手法は、国際的に広く批判されている。そこに浮かび上がってくるのは、資源を外交ツールとして用い、ロシア政府の戦略資源の支配権を再確立し、エリツィン政権時代の外国との契約を見直そうとするプーチン政権の戦略である。