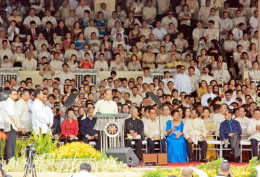イラン核合意と北朝鮮の教訓
―― 合意を政治的に進化させるには
2015年5月号

イランとの核合意にとって、北朝鮮への核外交が失敗したことの中核的教訓とは何か。それは、最善の取引を交わしたとしても、合意そのものは外交ドラマのプレリュードにすぎないということだ。テヘランが平壌と同じ道を歩むのを阻むには、今後、テヘランがこれまでとは抜本的に異なる新しいアメリカや地域諸国との関係、国際コミュニティとの関係を築いていけるようにしなければならない。アメリカは北朝鮮との核合意を結びながらも、政治的理由から合意を適切に履行せず、結局、北朝鮮は核開発の道を歩み、核保有を宣言した。米議会からリヤド、エルサレムにいたるまで、イランとの核合意に反対する勢力がすでに動きだしている。相手国との関係の正常化こそが、核開発の凍結を実現する最善の方法であることを忘れてはならない。そうできなかったことが北朝鮮外交失敗の本質であり、この教訓をイランとの外交交渉に生かしていく必要がある。