- トップページ
- Issue in this month
- 2011年9月号(2)チェルノブイリからフクシマへ―教訓は生かされたのか
Issue in this month
2011年9月号(2)チェルノブイリからフクシマへ―教訓は生かされたのか
2011-09-08
チェルノブイリからフクシマへ―教訓は生かされたのか
―原発危機への対応が露わにした日本の統治危機
2011.9 .8公開
<統治構造の危機>
菅直人前総理は、最近の読売新聞とのインタビューで「事故前からいろんな意見があったのに、しっかりした備えをしなかったという意味で人災だ」と事故を振り返っている。曖昧な表現だが、「全電源喪失」を想定していなかったという点で事故は人災だったという意味なら、そのとおりだろう。1986年のチェルノブイリのケースも、電源喪失を想定した安全措置の動作実験をした結果、皮肉にも原子炉を制御できなくなり、大事故が起きている。
だが、原発危機が国境を越えた余波を伴う国際的な危機であり、必然的に国際的な対応が必要なことを、おそらく日本政府は理解していなかったように思える。そうだとすれば、これも人災だし、さらにいえば、そうした国際的危機への対応を民間の原発オペレーターに委ねたことも、危機を緩和できる可能性のあったアメリカ、フランス、ロシアからの技術支援の申し出を結果的に受け入れなかったことも深刻な人災だろう。
もちろん、経済産業省原子力保安院と原子力オペレーターの微妙で密接な関連ゆえに、政府自身、情報をもっていなかった可能性もある。だが、東北や関東だけでなく、周辺国、あるいは世界に影響を与える国際的危機が国内で起きているのに、政府が情報を持っていなかったとすれば、これは、非常に深刻な統治構造上の空白がこの国に存在することを意味する。
事態をさらに複雑にしたのが、迅速な情報公開が行われず、説明責任が果たされなかったことだ。例えば、各国の専門家やアメリカ政府を含む多くの諸国は、早ければ3月11日遅くとも3月16日までには、フクシマ第一原子力発電所でメルトダウンが起きていると確信していた(現実には、一号機のメルトダウンとメルトスルーの可能性が言及されたのは5月13日。それも政府ではなく、東電の発表だった)。
しかも、断片的な放射能拡散や放射能汚染の情報公開が、「直ちに健康に及ぼすレベルではない」という決まり文句とともに進められたため、政府への市民の不信を高めるとともに、放射能被曝を危険視する人々と、気にしない人々へと社会が二分されてしまった。
社会がパニックに陥るのを回避するという点では、こうした政府のやり方は成功だったかもしれないが、その結果、将来における市民の健康被害を限りなく大きくしてしまっている恐れがある。
悲しいことに、この6ヶ月間で明らかになったのは、地震と津波、そして原発危機という未曾有の危機を前に、被災者支援、原発危機の安定化、経済の再建と復興というアジェンダを同時多発的に進めるキャパシティも構造も日本には存在しないという現実でしかない。これは、危機を全般的に捉えた上で、分類し、それぞれの課題に具体的に対処していくという国家安全保障政策の意識と構造が戦後の日本では希薄なためかもしれない。
<ソビエトはどのような事故対策をとったか>
アメリカの核不拡散問題の専門家、ベネット・ランバーグは、チェルノブイリから4-6カ月後にまとめた「原発事故が子供たちと経済に与えた影響―― チェルノブイリの教訓 (1986年発表論文)」でソビエトによる原発事故への対応を次のように描写している。
 4月26日、爆発後のチェルノブイリ原発4号炉。手前がタービン施設。
4月26日、爆発後のチェルノブイリ原発4号炉。手前がタービン施設。
事故後に現場にかけつけた250人の消防士によって、4号炉の炉心内で燃えている黒鉛を別にすれば、すべての火災は午後6時35分までに鎮火した。その後、黒鉛の10%を燃焼させた大火災による放射能の拡散を封じ込める闘いが始められた。状況を何とか管理するまで2週間がかかった。最終的に、炉心にあった放射性物質の3―4%が大気中に拡散した。具体的には、放射性ヨウ素の15―20%、放射性セシウムの10―220%、さらに3%のプルトニウムを含む他の放射性同位元素の5・6%近くが大気中に拡散した。
放射性物質の大気への拡散の4分の1は最初の1日で起きており、その後2週間で、残りの4分の3が大気中に放出された。最終的な解決策は、黒鉛火災を止めることだった。まず、核分裂反応を止める必要があった。
40トンの炭化ホウ素がヘリコプターから投下された。さらに、原子炉に向かって800トンのドロマイト、2400トンの鉛、1800トンの粘土と砂が投下された。一方で、瓦礫の下にある原子炉を冷やし、原子炉の底がメルトスルーするのを避けるためにソビエトのエンジニアたちは液体窒素を送り込んだ。原子炉の底が溶ければ、地下50フィートにある地下水源が汚染される恐れがあった。・・・・(B・ランバーグ)原発事故が子供たちと経済に与えた影響―― チェルノブイリの教訓 (1986年発表論文)
<6カ月後の日本>
事故から半年後の日本の現状の一部は次のように描写できるかもしれない。
冷却化の進展によって爆発の危機は低下し、危機は安定化に向かいつつある。だが、フクシマでの原発事故による放射性物質の大気・海洋への拡散の規模は、いまやチェルノブイリのそれを上回りつつある。
例えば、米エネルギー前上級政策顧問のロバート・アルバレズは6月10日の時点で「日本政府は4000万キューリーの放射性物質が拡散されたことをIAEAに対して認めたが、海洋へと流れだした2000万キューリーの放射性物質を無視している」と指摘している(注1)つまり、すでに6月の時点で日本では6000万キューリーの放射性物質が拡散されており、これは日本での放射性物質の拡散が、チェルノブイリ事故で拡散した放射性物質5000万キューリーを上回っていることを意味する。
しかも、土壌汚染に加えて、原子炉がメルトスルーを起こしているため、地下水も汚染されているリスクが高いし、廃炉に向けた具体的道筋はたっていない。
食品・飲料水中のセシウム137の許容濃度(ベクレル/Kg)
 厚生労働省発表「飲食物摂取制限に関する指標」、
厚生労働省発表「飲食物摂取制限に関する指標」、
「ウクライナでの事故への法的取り組み」オレグ・ナスビット、今中哲二(表8)
のデータをもとに作成。
食物連鎖、環境連鎖に放射性物資が入り込むことで汚染が広がりをみせるなか、暫定基準の数値が引き上げられ、その結果、放射線の内的被曝を危険視する人々と、気にしない人々へと社会が二分されつつある。日本政府の主張とは逆に、米国科学アカデミーは、「放射線被曝には、これ以下なら安全」といえる量はないというリポートを出している。(注2)ランバーグも、「低レベル放射線被曝がどのような影響を人体に与えるかについては、専門家の間にもコンセンサスはない」と指摘している。
結局のところ、現在の日本、特に東北と関東では、何を食べ何を食べないか、何をして何をしないか、個々人が判断するしかない状況にある。
落ち葉を集めてたき火で焼き芋をつくるのどかな風景、公園に落ちているドングリやギンナンを人々が拾う日常的光景が、東北ではもちろん、関東、おそらくは中部地方でも潜在的に大きなリスクを伴うことを、なぜ市民を守るべき立場にある政府は広報しないのだろうか。
日本政府がチェルノブイリの教訓を学んでいるかどうか、読者のみなさまに判断していただきたい。
(文責 竹下興喜、フォーリン・アフェアーズ・ジャパン)
(1) http://www.democracynow.org/2011/6/10/as_japan_nuclear_crisis_worsens_citizen
(2) http://www4.nationalacademies.org/news.nsf/isbn/030909156X?OpenDocument 、 http://books.nap.edu/catalog/11340.html
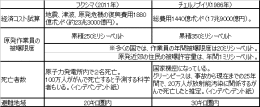 インデペンデント紙:Why the Fukushima disaster is worse than Chernobyl
インデペンデント紙:Why the Fukushima disaster is worse than Chernobyl
―原発危機への対応が露わにした日本の統治危機
2011.9 .8公開
<統治構造の危機>
菅直人前総理は、最近の読売新聞とのインタビューで「事故前からいろんな意見があったのに、しっかりした備えをしなかったという意味で人災だ」と事故を振り返っている。曖昧な表現だが、「全電源喪失」を想定していなかったという点で事故は人災だったという意味なら、そのとおりだろう。1986年のチェルノブイリのケースも、電源喪失を想定した安全措置の動作実験をした結果、皮肉にも原子炉を制御できなくなり、大事故が起きている。
だが、原発危機が国境を越えた余波を伴う国際的な危機であり、必然的に国際的な対応が必要なことを、おそらく日本政府は理解していなかったように思える。そうだとすれば、これも人災だし、さらにいえば、そうした国際的危機への対応を民間の原発オペレーターに委ねたことも、危機を緩和できる可能性のあったアメリカ、フランス、ロシアからの技術支援の申し出を結果的に受け入れなかったことも深刻な人災だろう。
もちろん、経済産業省原子力保安院と原子力オペレーターの微妙で密接な関連ゆえに、政府自身、情報をもっていなかった可能性もある。だが、東北や関東だけでなく、周辺国、あるいは世界に影響を与える国際的危機が国内で起きているのに、政府が情報を持っていなかったとすれば、これは、非常に深刻な統治構造上の空白がこの国に存在することを意味する。
事態をさらに複雑にしたのが、迅速な情報公開が行われず、説明責任が果たされなかったことだ。例えば、各国の専門家やアメリカ政府を含む多くの諸国は、早ければ3月11日遅くとも3月16日までには、フクシマ第一原子力発電所でメルトダウンが起きていると確信していた(現実には、一号機のメルトダウンとメルトスルーの可能性が言及されたのは5月13日。それも政府ではなく、東電の発表だった)。
しかも、断片的な放射能拡散や放射能汚染の情報公開が、「直ちに健康に及ぼすレベルではない」という決まり文句とともに進められたため、政府への市民の不信を高めるとともに、放射能被曝を危険視する人々と、気にしない人々へと社会が二分されてしまった。
社会がパニックに陥るのを回避するという点では、こうした政府のやり方は成功だったかもしれないが、その結果、将来における市民の健康被害を限りなく大きくしてしまっている恐れがある。
悲しいことに、この6ヶ月間で明らかになったのは、地震と津波、そして原発危機という未曾有の危機を前に、被災者支援、原発危機の安定化、経済の再建と復興というアジェンダを同時多発的に進めるキャパシティも構造も日本には存在しないという現実でしかない。これは、危機を全般的に捉えた上で、分類し、それぞれの課題に具体的に対処していくという国家安全保障政策の意識と構造が戦後の日本では希薄なためかもしれない。
<ソビエトはどのような事故対策をとったか>
アメリカの核不拡散問題の専門家、ベネット・ランバーグは、チェルノブイリから4-6カ月後にまとめた「原発事故が子供たちと経済に与えた影響―― チェルノブイリの教訓 (1986年発表論文)」でソビエトによる原発事故への対応を次のように描写している。
 4月26日、爆発後のチェルノブイリ原発4号炉。手前がタービン施設。
4月26日、爆発後のチェルノブイリ原発4号炉。手前がタービン施設。事故後に現場にかけつけた250人の消防士によって、4号炉の炉心内で燃えている黒鉛を別にすれば、すべての火災は午後6時35分までに鎮火した。その後、黒鉛の10%を燃焼させた大火災による放射能の拡散を封じ込める闘いが始められた。状況を何とか管理するまで2週間がかかった。最終的に、炉心にあった放射性物質の3―4%が大気中に拡散した。具体的には、放射性ヨウ素の15―20%、放射性セシウムの10―220%、さらに3%のプルトニウムを含む他の放射性同位元素の5・6%近くが大気中に拡散した。
放射性物質の大気への拡散の4分の1は最初の1日で起きており、その後2週間で、残りの4分の3が大気中に放出された。最終的な解決策は、黒鉛火災を止めることだった。まず、核分裂反応を止める必要があった。
40トンの炭化ホウ素がヘリコプターから投下された。さらに、原子炉に向かって800トンのドロマイト、2400トンの鉛、1800トンの粘土と砂が投下された。一方で、瓦礫の下にある原子炉を冷やし、原子炉の底がメルトスルーするのを避けるためにソビエトのエンジニアたちは液体窒素を送り込んだ。原子炉の底が溶ければ、地下50フィートにある地下水源が汚染される恐れがあった。・・・・(B・ランバーグ)原発事故が子供たちと経済に与えた影響―― チェルノブイリの教訓 (1986年発表論文)
<6カ月後の日本>
事故から半年後の日本の現状の一部は次のように描写できるかもしれない。
冷却化の進展によって爆発の危機は低下し、危機は安定化に向かいつつある。だが、フクシマでの原発事故による放射性物質の大気・海洋への拡散の規模は、いまやチェルノブイリのそれを上回りつつある。
例えば、米エネルギー前上級政策顧問のロバート・アルバレズは6月10日の時点で「日本政府は4000万キューリーの放射性物質が拡散されたことをIAEAに対して認めたが、海洋へと流れだした2000万キューリーの放射性物質を無視している」と指摘している(注1)つまり、すでに6月の時点で日本では6000万キューリーの放射性物質が拡散されており、これは日本での放射性物質の拡散が、チェルノブイリ事故で拡散した放射性物質5000万キューリーを上回っていることを意味する。
しかも、土壌汚染に加えて、原子炉がメルトスルーを起こしているため、地下水も汚染されているリスクが高いし、廃炉に向けた具体的道筋はたっていない。
食品・飲料水中のセシウム137の許容濃度(ベクレル/Kg)
 厚生労働省発表「飲食物摂取制限に関する指標」、
厚生労働省発表「飲食物摂取制限に関する指標」、「ウクライナでの事故への法的取り組み」オレグ・ナスビット、今中哲二(表8)
のデータをもとに作成。
食物連鎖、環境連鎖に放射性物資が入り込むことで汚染が広がりをみせるなか、暫定基準の数値が引き上げられ、その結果、放射線の内的被曝を危険視する人々と、気にしない人々へと社会が二分されつつある。日本政府の主張とは逆に、米国科学アカデミーは、「放射線被曝には、これ以下なら安全」といえる量はないというリポートを出している。(注2)ランバーグも、「低レベル放射線被曝がどのような影響を人体に与えるかについては、専門家の間にもコンセンサスはない」と指摘している。
結局のところ、現在の日本、特に東北と関東では、何を食べ何を食べないか、何をして何をしないか、個々人が判断するしかない状況にある。
落ち葉を集めてたき火で焼き芋をつくるのどかな風景、公園に落ちているドングリやギンナンを人々が拾う日常的光景が、東北ではもちろん、関東、おそらくは中部地方でも潜在的に大きなリスクを伴うことを、なぜ市民を守るべき立場にある政府は広報しないのだろうか。
日本政府がチェルノブイリの教訓を学んでいるかどうか、読者のみなさまに判断していただきたい。
(文責 竹下興喜、フォーリン・アフェアーズ・ジャパン)
(1) http://www.democracynow.org/2011/6/10/as_japan_nuclear_crisis_worsens_citizen
(2) http://www4.nationalacademies.org/news.nsf/isbn/030909156X?OpenDocument 、 http://books.nap.edu/catalog/11340.html
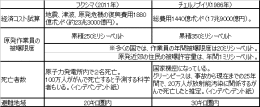 インデペンデント紙:Why the Fukushima disaster is worse than Chernobyl
インデペンデント紙:Why the Fukushima disaster is worse than Chernobyl 




