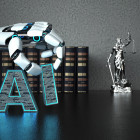Drop of Light / Shutterstock.com
2016.03.28 Mon
ユーラシアに迫り来るアナキー
―― ユーラシアのカオスと中ロの
対外強硬路線
クレムリンでのクーデター、ロシアの部分的解体、中国西部でのイスラムテロ、北京における派閥抗争、中央アジアの政治的混乱など、ワシントンは、カオスの到来に備えるべきだ。冷戦、ポスト冷戦という比較的穏やかな時代は過ぎ去り、ユーラシアの解体に伴うアナキーに派生する長期的な大国間紛争の時代に備えるべきだろう。(カプラン)
プーチンは、ユーラシア経済連合構想でEUに対抗しようとしている。だが、ロシアとの対立にばかり気をとられていると、思わぬ伏兵・中国に足をすくわれることになる。海と陸のシルクロード構想を通じて、ユーラシアを影響圏に組み込もうと試みる中国はすでに東ヨーロッパでのプレゼンスを高めることに成功している。(クラステフ/レナード)
ヨーロッパは2012年に起きたような、需要のピーク時に深刻な天然ガス供給不足に陥るといった事態を回避するためにも、新たな天然ガスの供給を確保したいと考えている。アメリカの中央アジアへの関心が希薄になっているとしても、ヨーロッパは旧ソビエト圏での影響力を形作ることを諦めるべきではない。(シャファー)