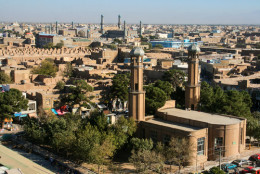CFRミーティング
アフガン撤退戦略の見直しを
2010年12月号

「カルザイ政権とのパートナーシップが不安定で、パキスタンとも部分的なパートナーシップしか結べていない以上、われわれは何度も同じことを繰り返して、異なる結果が出るのを期待してはならない。やり方を変える必要がある。・・・・さらに、ラシュカレトイバのことも忘れてはいけない。これまではカシミールを拠点にインドを攻撃してきた・・・ラシュカレトイバは、ハッカニ・ネットワーク同様に、インドだけでなくアメリカを敵視している。私があえてハッカニ・ネットワークについてここで述べたのは、今度、ムンバイタイプのテロが起きれば、インドは(パキスタンに対して)具体的な反撃に出ると考えるからだ。しかも、ラシュカレトイバはアルカイダの同盟勢力だ。アルカイダにとって、インドとパキスタンを戦わせることにどのような利点があるかを考えるべきだ」(R・アーミテージ)