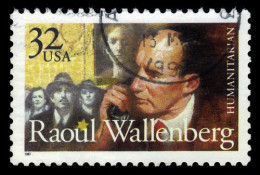現在の中国とロシアは、日独が第二次世界大戦に敗れた1945年以降、姿を消していた権威主義的資本主義パワーの再来にほかならない。日独の場合、アメリカを相手にするには、人口、資源、潜在力があまりに小さすぎたが、中国とロシアは、日独よりもはるかに国家規模が大きいし、そもそも、権威主義体制下の資本主義のほうが民主体制下の資本主義よりも効率が高い。実際、日独という権威主義的資本主義国家が戦後も存続していれば、アメリカにとって、共産主義中央統制経済のソビエト以上に大きな脅威と課題をつくりだしていたかもしれない。中国とロシアに代表される権威主義的な資本主義国家が、近代性の進化をめぐってリベラルな民主主義の代替策を提示することになるかもしれないし、グローバル経済に自分のルールで関与するようになるかもしれない。リベラルな民主主義が、最終的に勝利を収めるという保証はどこにもなく、権威主義的資本主義がリベラルな民主主義に代わる魅力的な選択肢とみなされるようになる可能性もある。